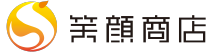プロローグ
えっ!鹿って泳げるの?
ある日、インターネットで動画を見て私は驚いた。一頭の鹿が、力強く水をかき、海を泳いでいく。その姿は、孤高で、どこか切実な意志に満ちていた。
なぜ、鹿はその安住の地を離れ、危険を冒してまで別の土地を目指すのか。縄張り争いに負けたからか。それとも、食料が尽きたからか。あるいは、ただ新天地を求める本能なのか。
その時、ふと思った。この姿は、かつての人類にも同じようにあったのではないか、と。アフリカで生まれた我々の祖先が、何万年もの歳月をかけて世界中に広がっていった「グレートジャーニー」。その原動力もまた、こうした「故郷を去る」という決断の連続だったのかもしれない。
この素朴な疑問から、私はAIとの対話を始めた。それは、鹿の習性から人類の歴史を遡り、やがて現代日本が抱える「人口減少」という巨大な壁、そして国家の未来をめぐる究極の選択へと繋がる、壮大な知の冒険となった。これは、その対話の物語である。
第1章:自然の掟と人間の旅路
私たちの対話は、鹿の習性の確認から始まった。
「決闘に勝ったオスが、複数のメスとハーレムを築いて子孫を繁栄させ、負けたオスはそこから出ていく」。
これは、ニホンジカなど多くの鹿に見られる、種の存続のための極めて合理的で力強いシステムだ。 秋、繁殖期を迎えたオスは「ラット」と呼ばれ、その力を示すために激しく角を突き合わせる。 勝者は子孫を残す権利を独占し、敗者や若いオスは群れを追われる。 強い遺伝子だけが次世代へと受け継がれていく、この非情とも思える掟こそが、種を力強く維持している。
そして、「鹿が海を渡る」という現象。これもまた、事実だった。鹿は泳ぎが得意で、実際に日本の慶良間諸島のケラマジカなどが、島々を泳いで渡ることが知られている。 もちろん、何十キロもの大海原を渡るわけではない。 しかし、食料の不足や個体数の増加といった、生息地が飽和した「必要性」に迫られた時、彼らは新天地を求めて海に飛び込むのだ。
この姿は、かつての人類に驚くほど重なる。約30万年前にアフリカで誕生した現生人類ホモ・サピエンスは、なぜ故郷を離れ、世界中へと拡散していったのか。 「縄張り争いに負けたものが去った」というイメージは、本質の一部を捉えているだろう。 集団内の対立や人口圧が、彼らを新たな土地へと押し出した。 まるで、ハーレムを追われたオス鹿のように。
その数万年に及ぶ人類の壮大な旅路の記憶は、私たちの細胞の奥深くに、今もなお刻み込まれている。父から息子へとほぼそのまま受け継がれる「Y染色体DNA」と、母から全ての子供へ受け継がれる「ミトコンドリアDNA」。 これらのDNAに刻まれた変異の系譜(ハプログループ)を辿ることで、我々の遠い祖先がどのようなルートを辿ってこの日本列島にたどり着いたのか、その遺伝的な足跡を知ることができるのだ。
しかし、人間は鹿ではなかった。私たちの祖先は、単に力で劣るものが去るという単純な社会に生きていたわけではない。
第2章:家族のかたち –– 明治日本の決断と現代フランスの選択
シカの社会は、本能と力の序列で成り立つ。 だが、人間の社会は、たとえ原始の時代であっても、血縁、協力、そして複雑なコミュニケーションといった社会的ルールの上に成り立っていた。 生き残るための「協力」と「分業」。 そして、長い子育て期間を支えるための、男女間の「長期的なペアボンド(絆)」。 これらが、人間を人間たらしめた決定的な違いだった。
社会が成熟するにつれ、人間はこの「家族」というシステムを精緻化させていく。江戸時代までの日本では、武士や公家、裕福な商人などの支配階級において、一人の男性が正妻のほかに複数の「妾(めかけ)」や「側室」を持つことが公然と認められていた。 それは、家の存続と権力の象徴であった。
しかし、明治維新を経て、日本は西洋の近代国家を目指す中で、大きな決断を下す。1898年(明治31年)、新たに施行された民法によって、法的に結婚している者が重ねて結婚すること(重婚)が明確に禁止され、戸籍から「妾」の欄が消えた。 ここに、現代まで続く日本の「一夫一婦制」が法的に確立されたのだ。それは、社会の安定と近代化のための、国家による家族観の「標準化」だった。
一方で、同じく少子化という課題に直面した国、フランスは、全く異なる道を選んだ。
フランスの成功の鍵は、日本の「標準化」とは真逆の「多様化の受容」にあった。彼らは、法律婚という形に固執しなかった。1999年に導入された「PACS(パックス/連帯市民協約)」は、結婚よりも柔軟なパートナーシップを法的に認める制度だ。 そして何より決定的だったのは、結婚しているか否かにかかわらず、「どんな生まれ方であっても、全ての子供は平等な権利を持つ」という原則を社会の隅々まで徹底させたことだ。
かつては日本と同様に存在した、婚外子(婚姻関係にない男女間の子供)への法的な差別を完全撤廃。 加えて、子供の数が多いほど世帯の税負担が劇的に軽くなる「N分N乗方式」という強力な経済的支援、そして3歳からほぼ無償で通える「保育学校」という徹底した両立支援。 これら重層的な政策パッケージの結果、フランスでは生まれる子供の6割以上が婚外子となり、出生率の回復に成功した。
日本の「厳格な制度化」と、フランスの「柔軟な多様化」。少子化という同じ課題に対する、実に対照的なアプローチだ。
第3章:国家の岐路 –– 合理的な処方箋が効かない理由
では、日本もフランスのモデルを導入すればいいではないか?対話は、現代日本が直面する核心的なジレンマへと踏み込んでいく。
この「合理的な処方箋」が、日本では機能しない。その理由は、単なるお金の問題ではなく、この国の社会観、法律、政治に深く根差した、複数の巨大な壁の存在にある。
[1] 価値観の壁
日本には、法律婚をした夫婦が同じ戸籍に入り、子供がその戸籍に入る形こそが「正式な家族」という意識が今なお非常に強い。 フランスの婚外子比率が60%を超えるのに対し、日本はわずか2.4%。 この数字は、社会の受容度の圧倒的な差を物語る。PACSのような制度や婚外子を「当たり前の家族の形」として受け入れるには、まだ大きな心理的抵抗がある。
[2] 法律・制度の壁
日本の税制は、個人の所得に課税する「個人単位課税」が基本だ。フランスの強力な優遇税制「N分N乗方式」は、世帯の所得を合算して家族の人数で割る「世帯単位課税」であり、根本思想が異なる。 これを導入するには、日本の税制の根幹を作り変えるに等しい、途方もない法改正が必要になる。
[3] 財源・政治の壁
フランス並みの手厚い支援を実現するには、莫大な財源が必要だ。 すでに巨額の財政赤字を抱え、高齢化で社会保障費が増え続ける日本で、その財源をどう確保するのか。消費税の大幅引き上げなど、国民に大きな痛みを強いる決断が不可欠となり、政治的な合意形成は極めて困難だ。
私たちは対話の中で、「一夫多妻制の復活」や「子供の18歳までの完全生活保証」といった、さらに大胆なアイデアも検討した。しかし、前者は人権と憲法に反し、深刻な社会不安を招く。 後者は、年間数十兆円という天文学的な予算を要し、財政的に実現不可能だ。
結局、あらゆる「合理的」で「抜本的」に見える解決策は、日本の「現実」という分厚い壁の前に、ことごとく跳ね返されてしまう。この「分析」と「現実」の間の、埋めがたい絶望的な断絶。それこそが、日本の閉塞感の正体なのかもしれない。
第4章:いかにして衰退するのか –– 究極の選択
合理的な処方箋が機能しないと悟った時、対話は最も深く、そして最も残酷な核心へと至った。「このままでは、じり貧になる」。この認識は、もはや問いではない。それは、ほぼ確定した未来だ。
だとすれば、今、私たちが無意識のうちに迫られている選択は、「どうすれば成長できるか」ではない。「どうせ衰退するなら、どちらの衰退を選ぶのか」という、究極の問いである。
選択肢A:緩やかな衰退 これが、現在の道だ。財政規律と社会保障のバランスを取りながら、痛みを少しずつ先送りし、時間をかけてゆっくりと沈んでいく。 急激な社会混乱はなく、予測可能で、「管理的」な衰退とも言える。しかし、その先に希望もダイナミズムもない。未来世代への負担の先送りを意味する、「確実な失敗」への道である。
選択肢B:危険な賭け これは、「緩やかな衰退」という運命に抗う道だ。財政破綻や円の信認失墜という致命的なリスクを覚悟の上で、「赤字は国債で賄う」と割り切り、社会構造を根底から覆すような抜本改革に打って出る。 失敗すれば、円は暴落し、制御不能なインフレが国民生活を破壊する「急激な崩壊」を招く。 しかし、万に一つ、成功の可能性を秘めている。
どちらの道も、地獄かもしれない。だからこそ、この問いが政治の舞台で真正面から語られることはない。だが、この国の誰もが、その選択を無言のうちに迫られているのではないだろうか。
対話の終わりに、私は思った。
日本の未来を繋ぐ子供たちに、希望をのこせるかどうかが決め手ではないかと。100%じり貧で崩壊する道を甘んじて受け入れるのか。それとも、極端な変化で今を生きる我々自身が大きなリスクを負ってでも、子供たちが生き残る可能性のある道を選ぶのか。
前者は、今を生きる我々の安定と引き換えに、異議を唱えられない子供たちに、先送りにしたツケを全て渡すという選択だ。 後者は、未来の可能性のために、今を生きる我々自身が、激動と不確実性の痛みを全て引き受ける覚悟をするという選択だ。
どちらが、未来に対してより誠実な姿勢なのか。
エピローグ
一頭の鹿が、海を渡る。その先には、豊かな新天地があるかもしれないし、力尽きて海に沈むだけの運命が待っているのかもしれない。ただ、生きるための本能が、彼を突き動かす。
今の日本もまた、この鹿のように、大きな海を前に立ち尽くしている。違うのは、私たちの決断が本能ではなく、理性と、そして次世代への責任という倫理観に裏打ちされていなければならないことだ。
緩やかに沈みゆく船に留まり続けるのか。それとも、嵐の海に、小さな希望を乗せた舟を漕ぎ出すのか。
答えはない。しかし、この痛みを伴う問いから目を逸らさず、社会全体のテーブルに乗せる勇気を持つこと。それこそが、未来への責任を果たすための、第一歩なのだろう。シカのささやかな問いから始まったAIとの対話は、私にそう強く教えてくれた。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役