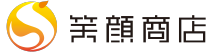はじめに:『マッサン』が描いた夢の場所へ
NHKで放送された連続テレビ小説『マッサン』。多くの人が、その物語に心を揺さぶられたのではないでしょうか。日本のウイスキーづくりの父であり、ニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝翁翁と、彼を支え続けたスコットランド人の妻リタの生涯を描いたこのドラマは、単なる成功物語ではありませんでした。それは、夢を追いかけることの情熱、困難に立ち向かう不屈の精神、そして深い愛情の物語でした。
その物語の原点ともいえる場所、竹鶴政孝翁翁が理想のウイスキーづくりを追求するために生涯を捧げた聖地が、北海道の余市町にあります。1934年、彼が情熱のすべてを注ぎ込んで設立したニッカウヰスキー発祥の地、「余市蒸留所」。
先日、ついにその場所を訪れる機会に恵まれました。普段、私がウイスキーを頻繁に飲むわけではありません。しかし、竹鶴政孝翁という人物の「本物」を追求する信念と、その揺るぎないものづくりへの姿勢に強く惹かれ、彼の夢が詰まった場所をこの目で見て、肌で感じてみたいと思ったのです。
歴史が息づく、美しい蒸留所の佇まい
新千歳空港から電車を乗り継ぎ、約2時間。JR余市駅から徒歩3分。赤レンガの建物と特徴的なパゴダ屋根(キルン塔)が見えてきます。そこがニッカウヰスキー余市蒸留所です。
正門をくぐると、まるで時が止まったかのような、静かで荘厳な空気が流れています。創業当時の面影を色濃く残す石造りの貯蔵庫や、赤レンガの建物群が、訪れる者を優しく迎え入れてくれます。これらの歴史的建造物の多くは、国の重要文化財や登録有形文化財に指定されており、その一つ一つがニッカウヰスキーの歩んできた歴史の証人です。
特に印象的だったのは、今もなおウイスキーづくりを支える施設が現役で稼働していること。蒸留所全体が、単なる観光施設ではなく、「生きている工場」としての気概と誇りに満ち溢れているのです。
非常に人気が高い予約制のガイドツアーは、ウイスキーの製造工程や歴史について深く知ることができるため、すぐに満席になってしまうほどの盛況ぶりです。専門のガイドさんの話を聞きながら、甘く香ばしい香りが漂う施設を巡れば、ニッカウヰスキーへの理解がより一層深まることでしょう。訪問を計画される際は、早めの予約をおすすめします。
ウイスキーづくりの神髄に触れる – ニッカミュージアム探訪
ガイドツアーに参加せずとも、この蒸留所の魅力は十分に堪能できます。その中心となるのが「ニッカミュージアム」です。
館内に足を踏み入れると、まずニッカのウイスキーづくりの神髄が紹介されています。原料である大麦の選定から、発酵、蒸留、そして樽での熟成に至るまで、一切の妥協を許さない職人たちのこだわりが、詳細な展示からひしひしと伝わってきます。
そして、このミュージアムのもう一つの核となるのが、創業者・竹鶴政孝翁の物語です。広島の造り酒屋の三男として生まれた彼が、いかにしてウイスキーづくりに目覚めたのか。単身スコットランドへ渡り、現地の大学で化学を学びながら、いくつもの蒸留所の門を叩いてウイスキーづくりの秘伝を学び取った留学時代。そして、そこで運命の女性リタと出会い、国際結婚を乗り越えて共に日本へ帰国するまでのドラマチックな道のりが、貴重な資料と共に紹介されています。
彼の残した言葉や、愛用の品々、リタ夫人との心温まるエピソードの数々に触れていると、彼のウイスキーづくりにかけた情熱が、まるで自分自身の心にも宿るような感覚を覚えました。
香りの誘惑 – 至福のテイスティング体験
ミュージアムを見学し、竹鶴政孝翁の情熱に触れた後には、お待ちかねのテイスティングです。館内には有料のテイスティングバーがあり、余市蒸留所でしか味わえない限定品や、希少なシングルモルトウイスキーを味わうことができます。
普段はウイスキーを飲み慣れていない私ですが、ここまで来て体験しない手はありません。スタッフの方にアドバイスをいただきながら、いくつかの種類を試してみることにしました。グラスに注がれた琥珀色の液体をゆっくりと鼻に近づけると、銘柄ごとに全く異なる、複雑で豊かな香りが立ち上ります。スモーキーな香り、果実のような甘い香り、樽由来の深い香り…。
一口含んでみると、その味わいの奥深さに驚かされます。アルコールの刺激とともに、凝縮された旨味と香りが口の中に広がり、長い余韻を残していきます。正直なところ、これまで私が知っていたウイスキーとは全くの別物でした。これが、竹鶴政孝翁が追い求めた「本物のウイスキー」なのかと、深く感動しました。
「ニッカ」に込められた、驚きの真実と不屈の精神
さて、蒸留所を巡る中で、私には一つの素朴な疑問が浮かんでいました。それは「ニッカ」という社名の由来です。てっきり「日本のウイスキー」の略か何かだろうと思っていたのですが、その本当の意味を知り、私は竹鶴政孝翁という人物の凄みを改めて思い知らされることになりました。
「ニッカ」とは、もともと「大日本果汁株式会社」の略称、「日果(にっか)」だったのです。
ウイスキーの会社が、なぜ果汁なのか?
その答えは、ウイスキーという酒の特性にありました。ウイスキーは、蒸留した原酒を樽に詰め、最低でも5年、長いものでは10年、20年と熟成させなければ製品になりません。つまり、工場を建ててウイスキーづくりを始めても、最初の5年間は売上が一切立たないのです。
この「死の谷」ともいえる期間を乗り越えるため、竹鶴政孝翁は余市周辺で豊富に採れるリンゴに目をつけました。ウイスキーの熟成を待つ間、リンゴジュースやリンゴ製品を製造・販売することで会社を支え、従業員の生活を守ったのです。
「日本に本物のウイスキーを根付かせたい」。そのあまりにも壮大で、あまりにも時間のかかる夢。5年間もビジネスとして成り立たないのならば、多くの人は諦めてしまうでしょう。しかし彼は諦めなかった。理想のウイスキーづくりという長期的な目標を見据えながら、足元の経営を安定させるための現実的な手段を講じたのです。
竹鶴政孝翁の哲学から学ぶ、現代を生きるヒント
彼のこの逸話は、単なるウイスキー会社の創業秘話にとどまりません。現代を生きる私たちにとっても、非常に重要な示唆を与えてくれます。
何か新しいことを始めようとするとき、私たちは必ず壁にぶつかります。夢や目標が大きければ大きいほど、その壁は高く、そして成果が出るまでの道のりは長くなります。ウイスキーづくりだけでなく、例えば農作物を育てることや、基礎研究、あるいは新しい事業の立ち上げなど、すぐに収益にならないものは世の中にたくさんあります。
そんな時、私たちはどうすればその壁を乗り越えられるのでしょうか?
竹鶴政孝翁のやり方は、その一つの答えを示してくれています。それは、「最終的なゴールから逆算して計画を立て、起こりうるリスクへの対策をあらかじめ講じておく」ということです。
彼は「5年後に最高のウイスキーを世に出す」というゴールを設定し、そこから逆算して、「では、その5年間をどうやって生き抜くか?」という課題に対する答えとして「リンゴジュースの製造」という具体的な策を打ち出しました。
これは、あらゆるビジネスや個人の目標達成において、成功の鍵を握る考え方ではないでしょうか。情熱や夢だけでは、現実は乗り越えられません。その情熱を現実の軌道に乗せるための、冷静な分析と緻密な戦略。この両輪があって初めて、事業や夢は大きな軌道に乗ることができるのだと、余市の地で深く感じさせられました。
おわりに – 余市で感じた、本物の情熱
ニッカウヰスキー余市蒸留所の訪問は、私にとって単なる工場見学ではありませんでした。それは、一人の男の生涯をかけた夢と、その夢を支えた人々の情熱に触れる、魂の旅でした。
ウイスキーの芳醇な香りと共に、この場所に満ちていたのは、困難に屈せず、本物を追求し続けた人間の揺るぎない精神です。
ウイスキーが好きな方はもちろんのこと、ものづくりに興味がある方、何か新しい挑戦をしようとしている方、そして大きな壁にぶつかっている方にこそ、ぜひ訪れてほしい場所です。竹鶴政孝翁がこの地に遺した夢の跡は、きっとあなたの心に、温かくも力強い火を灯してくれるはずです。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役