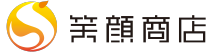「よく考えてから行動しなさい!」
子供の頃、親や先生から一度は言われたことのある言葉ではないでしょうか。石橋を叩いて渡るように、慎重に計画を立て、リスクを最大限に排除してから一歩を踏み出す。これが、これまでの日本社会における「正解」の一つだったように思います。
一方で、特にコロナ禍を経て、世の中の価値観は大きく変わりました。
「まずは動け。考えるのは行動しながらでいい」 「トライ&エラーを繰り返せ。完璧を目指すな」
まるで、これまでの教えと真逆のような言葉を、ビジネスの現場や自己啓発の分野で頻繁に耳にするようになりました。変化の激しい時代において、慎重に考えすぎることが、かえって機会損失に繋がるという考え方です。
では、一体どちらが正しいのでしょうか?
結論から言うと、「どちらも正しく、状況によって使い分けるべき」というのが僕の考えです。
この記事では、どのような時に「考えてから行動する」べきで、どのような時に「行動しながら考える」べきなのか、僕自身の経験や脳科学的な知見を交えながら、その最適な使い分けについて掘り下げていきたいと思います。
結論:「地図」を持っているか、「コンパス」しか持っていないか
この問題の答えは、あなたがこれから進む道に対して、明確な「地図」を持っているかどうかで決まります。
・考えてから行動するべき時:目的地までのルートが明確な「地図」を持っている(頭の中で成功への道筋がイメージできている)場合
・行動しながら考えるべき時:目的地はぼんやりしているが、進むべき方角を示す「コンパス」しか持っていない(頭の中でイメージができていない)場合
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
考えてから行動するべき時 – 脳の「現状維持バイアス」を乗り越える
まず、「考えてから行動する」べきなのは、頭の中で成功への道筋が具体的にイメージできているケースです。特に、これまでの「習慣」を変えたい時に、このアプローチは絶大な効果を発揮します。
というのも、私たちの脳は非常に省エネ好きで、できるだけ頭を使わずに済む「習慣(無意識の行動)」を好むからです。これを脳科学の世界では「現状維持バイアス」と呼びます。何も意識しないと、私たちは昨日と同じ行動を自動的に繰り返してしまうのです。
銀行振込で時間を無駄にした私の失敗談
最近の僕の経験をお話しします。
以前は、ある銀行口座から別口座にお金を移動させる際、わざわざ銀行に出向き、ATMでお金をおろして、別の銀行のATMに入金するという手間のかかる作業をしていました。
しかし最近、メインで使っているネット銀行の振込手数料が無料になったのです。これを使えば、スマホ一つで、いつでもどこでも、一瞬で資金移動が完了します。どう考えても、こちらの方が効率的で合理的です。頭の中では、その便利さを完全に理解していました。まさに「地図」を持っている状態です。
ところが、ある忙しい日のことでした。無意識のうちに、僕は以前の習慣通り、わざわざ時間を割いて銀行のATMをはしごしていたのです。途中で「あ、ネットでできたじゃん…」と気づいた時の徒労感といったらありません。忙しいからこそ効率化したいのに、無意識の習慣によって、貴重な時間をドブに捨ててしまったのです。
習慣を変えるには「意識的な思考」が不可欠
この経験からわかるように、たとえ新しい、より良い方法(地図)を知っていても、古い習慣という強力な自動操縦機能に私たちは簡単に引き戻されてしまいます。
この自動操縦を停止させ、新しいルートを脳に定着させるためには、「よし、今日はネットで振り込むぞ」という意識的な思考と行動が不可欠です。
脳科学的にも、新しい行動が習慣として定着するには、一般的に3週間から3ヶ月程度の期間が必要と言われています。この期間は、意識的に「考えてから行動する」ことで、脳の神経回路(ニューラルネットワーク)に新しい道を刻み込むためのトレーニング期間なのです。
・ダイエットや筋トレ:「今日はジムに行くぞ」と意識して行動する。
・勉強や読書:「寝る前の15分は本を読む」と決めて実行する。
・お金の使い方:「コンビニでは現金を使わずキャッシュレス決済にする」と意識する。
このように、変えたい習慣が明確で、そのための方法(地図)が分かっている場合は、まず「思考」を先行させ、意識的に行動をコントロールすることが成功への鍵となります。
行動しながら考えるべき時 – 未知の荒野で「道」を見つける
一方で、頭の中で成功のイメージが全く描けない時や、何をすべきかはっきりしないが、とにかく現状を打破しなければならない時は、「行動しながら考える」アプローチが有効です。
これは、自分がどこにいるのかも、目的地までの最適なルートも分からない、広大な荒野で「コンパス」だけを頼りに進むような状況をイメージしてください。
このような状況で、完璧な地図が出来上がるまで動かずにいたら、いつまで経っても最初の一歩を踏み出すことはできません。
行動が脳の「検索エンジン」を起動させる
なぜ、イメージできない時に行動が有効なのでしょうか?
それは、行動することで、脳の「海馬(かいば)」が活性化するからです。
海馬は、記憶や学習を司る、脳の司令塔のような部分です。私たちが何か新しい行動を起こすと、五感を通じて様々な情報(成功、失敗、他人の反応、予期せぬ発見など)が脳にインプットされます。
すると、海馬は「お、何やら新しいことが始まったぞ。関連情報を集めないと!」と活発に働き始め、まるで高性能な検索エンジンのように、これまで蓄積してきた記憶や知識の中から、目の前の課題解決に役立ちそうな情報を探し出そうとします。さらに、意識がその問題に向かうことで、街中の会話や書店の本のタイトルなど、日常のあらゆる情報の中から解決のヒント(専門用語で「カラーバス効果」と呼びます)を見つけやすくなるのです。
・新しいビジネスを始めたいが、アイデアがない → とりあえず興味のあるイベントに参加してみる、人に会って話を聞いてみる。
・自分のキャリアに悩んでいる → 副業サイトに登録してみる、未経験の分野のオンライン講座を受けてみる。
・人間関係を改善したい → いつもと違うコミュニティに顔を出してみる、話したことのない同僚に声をかけてみる。
最初の一歩は、どんなに小さくても構いません。その小さな「行動」が、脳のスイッチを入れ、思考を現実化させるための情報を集め始め、結果として進むべき「道」そのものを創り出していくのです。
「PDCA」と「OODA」- 状況に応じたサイクルの使い分け
この2つのアプローチは、ビジネスフレームワークである「PDCAサイクル」と「OODAループ」の関係に似ています。
・PDCAサイクル (Plan-Do-Check-Act) 計画(Plan)を立ててから実行(Do)し、評価(Check)、改善(Act)するという、品質管理や業務改善に適した手法です。これはまさに、地図を元に進む「考えてから行動する」アプローチと言えます。道筋が見えている場合に非常に有効です。
・OODAループ (Observe-Orient-Decide-Act) まず現状を観察(Observe)し、状況を判断(Orient)、意思決定(Decide)して、行動(Act)する。行動の結果を再び観察し、高速でサイクルを回していく、変化の激しい状況や、意思決定のスピードが求められる現場で有効な手法です。これは、コンパスを頼りに進む「行動しながら考える」アプローチです。
どちらが優れているというわけではなく、改善や効率化のように「計画」が立てられる場面ではPDCAを、新規事業や未知の挑戦のように「観察」から始めざるを得ない場面ではOODAを、というように使い分けることが肝心です。
まとめ:あなたは今、どちらのフェーズにいますか?
「考えてから行動する」か、「行動しながら考える」か。
その答えは、あなたの置かれている状況によって変わります。
もしあなたが、変えたい習慣や、達成したい目標への道筋(地図)が見えているのであれば、脳の現状維持バイアスに打ち勝つために、強い意志を持って「考えてから行動」してください。その意識的な行動の繰り返しが、やがて新しい習慣を創り上げます。
一方で、もしあなたが、何をすれば良いか分からず、ただ漠然とした不安や焦りを感じているのであれば、完璧な計画を待つ必要はありません。どんなに小さな一歩でもいいので、まずは「行動しながら考える」ことを始めてみてください。その行動があなたの脳を活性化させ、進むべき道を照らすヒントを集め始めてくれるはずです。
大切なのは、両者の特性を理解し、今の自分に必要なアプローチを柔軟に選択すること。
「考える」と「行動する」は、車の両輪のようなものです。時にはじっくり考え、時には大胆に行動する。そのバランス感覚を磨くことで、私たちはどんな時代でも、しなやかに、そして力強く、前に進んでいくことができるのではないでしょうか。
この記事が、あなたの次の一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役