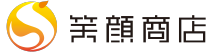旅の序章:ウニを目指す旅の、思わぬ寄り道
旅には、いつも確かな目的がある。今回の私の北海道行きも例外ではなかった。その目的とは、広大な大地で土にまみれて働く友人の、収穫の手伝いをすること。そしてもう一つ、シーズン最後の輝きを放つであろう、積丹(しゃこたん)のウニを心ゆくまで味わうこと。汗を流して働く友との再会、そして北の海の恵み。まさに、心と胃袋を満たすための、具体的で人間味あふれる計画だった。
ニッカウヰスキー余市蒸溜所は、正直に言って、当初の旅の計画には入っていなかった。友人の農作業を手伝い、さて次はいよいよメインイベントのウニだと盛り上がっていた時だ。ウニで有名な店へのルートを地図で確認していると、目的地の少し手前に「余市」という地名があることに気づいた。「あれ、ここって確か…」。そう、日本のウイスキーの聖地とも呼ばれる、あの蒸溜所がある場所だ。
ウイスキーは嫌いじゃない。むしろ、仲間と飲むハイボールは格別だ。だが、その歴史や製法を熱心に語れるほどの知識はない。「ウニの前に、ちょっと寄り道してみるか」。そんな軽い会話で、私たちの訪問はあっさりと決まった。あくまでメインディッシュは友人との再会と、とろけるようなウニ。蒸溜所見学は、その前のちょっとしたアペリティフ(食前酒)か、あるいは食後の散歩くらいの、そんな立ち位置だったのだ。
しかし、人生とは面白いもので、時として前菜がメインディッシュの記憶を塗り替えるほどの衝撃を与えることがある。この「ついで」の寄り道が、自分の凝り固まった常識を打ち破り、情報や人生そのものについて深く思索するきっかけになるとは。この時の私は、まだ目の前のウニ丼のことしか頭になかったのである。
潮風と麦芽の香りに満ちた聖地へ
友人とのそんな軽いノリでハンドルを切り、余市の町へ入ると、ひんやりと澄んだ空気に混じって、どこか甘く、香ばしい香りが車内まで漂ってきた。ウイスキーづくりに欠かせない、麦芽(モルト)の香りだ。そして、微かに感じる潮の香り。メインの目的ではなかったとはいえ、この独特な香りに包まれると、自然と心が躍るのを感じた。
重厚な石造りの正門をくぐると、そこはまるで時が止まったかのような、荘厳で美しい世界が広がっていた。人気のガイドツアーは残念ながら予約でいっぱいで参加できなかったが、かえってそれが良かったのかもしれない。私たちは自由気ままに、敷地内の地図を片手に散策を始めた。赤レンガの貯蔵庫、黒く煤けた屋根が特徴的なキルン塔(乾燥塔)、そして創業以来の姿を保ち続ける蒸溜棟。一つひとつの建物の前に立つたびに、説明書きを読み込み、自分たちのペースでウイスキーづくりの世界に浸っていった。特に心惹かれたのは、今では世界でも珍しいという「石炭直火蒸溜」の伝統を守る蒸溜棟だ。職人さんが石炭をくべる様子などを直接見ることは叶わなかったが、建物から漂う独特の熱気や、説明パネルに書かれたその製法へのこだわりに、見えない炎の力強さと、ニッカウヰスキーの哲学を垣間見た気がした。
ミュージアムでの邂逅、そして静かなる「悟り」
一通り自分たちの足で蒸溜所を巡った後、私たちは「ウイスキー博物館」へと向かった。館内には、ニッカウヰスキーの歴史を物語る貴重な資料や、年代物のボトルが美しく展示されている。竹鶴政孝と、彼を支え続けたスコットランド人の妻、リタの愛の物語に思いを馳せ、ウイスキーづくりに捧げられた彼らの人生に、軽い気持ちで立ち寄ったことを少し反省するほど、深く引き込まれていた。
そして、見学の締めくくりとして、お待ちかねの試飲の時間がやってきた。提供されたのは、余市蒸溜所の代表的な銘柄である「シングルモルト余市」など数種類。まずはストレートでその奥深い味わいに感動した後、少し加水して変化も楽しんでみようと、会場に用意されたウォーターサーバーに目をやった。すると、そこに私の常識を揺るがす光景が広がっていた。
水は2種類、用意されていたのだ。一つには「チェイサー用の水」と書かれ、傍らには氷がたっぷりと入ったアイスペール。これは見慣れた光景だ。しかし、もう一方には「水割り用の水」とはっきりと書かれており、そこには氷がなく、明らかに常温の水が用意されていた。
最初、その違いの意味が分からなかった。「なぜ、わざわざ分けているのだろう?」。普通、水割りといえば、氷と冷たい水を使うものではないのか。しかし、二つのピッチャーを交互に見つめるうち、雷に打たれたような閃きが頭を貫いたのだ。
もしかして、これこそが作り手の示す「正解」なのではないか、と。ウイスキーの繊細な香りと味を本当に楽しむためには、急激な温度変化をもたらす冷水ではなく、常温の水でゆっくりと割るべきだ、と。チェイサーはあくまで口をリフレッシュするための冷たい水。しかし、ウイスキーそのものに加えるのは、この常温の水。言葉による説明は一切ない。しかし、この明確な設えこそが、何より雄弁なメッセージに思えた。
私は、まるで答え合わせをするかのように、おそるおそる「水割り用の水」をグラスに数滴、ゆっくりと注ぎ入れてみた。そして、再びグラスに鼻を近づけた瞬間、息を呑んだ。先ほどまでとは明らかに違う、驚くほど豊かで華やかな香りが立ち上ってきたのだ。スモーキーさの奥に隠れていた、蜂蜜やバニラのような甘い香り、リンゴや洋梨を思わせるフルーティーなアロマが、次々と顔を覗かせる。一口飲んでみると、味わいも実にまろやか。アルコールの角が取れ、舌の上で余市モルトの持つ甘みとコクが、より一層豊かに、そして長く感じられるのだ。
誰かに教えられたのではない。目の前にある「本物」の設えから、自ら気づき、悟ったこの体験は、一方的に知識を与えられるよりも遥かに深く、私の心に刻み込まれた。
一杯の水割りが教えてくれた、情報との向き合い方
この静かなる発見は、私にとって、単なるウイスキーの知識以上の、もっと深く、本質的な問いを投げかけてきた。
なぜ、私はこれまでそのことに気づかなかったのだろうか。インターネットの記事や書籍の中で、目にしていたかもしれない。しかし、それは数多ある情報の一つとして、私の意識を通り過ぎていっただけだった。頭で「知っている」ことと、実際に現地で、本物に触れ、自ら「気づく」ことの間には、天と地ほどの隔たりがある。そのことを、この一杯の水割りは痛烈に教えてくれたのだ。
私たちは今、情報過多の時代を生きている。スマートフォンを開けば、専門家の意見、インフルエンサーのおすすめ、無数のレビューが津波のように押し寄せてくる。便利である反面、私たちはその情報の渦の中で、どれが本当に価値のある「一次情報」で、どれが伝聞や憶測に基づいた「二次情報」なのかを見極めるのが、非常に困難になっている。私たちは、その表層的な情報を受け取るだけで、まるで全てを理解したかのような錯覚に陥ってしまう危険性と、常に隣り合わせなのだ。
私が信じていた「水割り=冷水」という常識も、まさにその典型だった。それは、世間に広く浸透した「二次情報」的な飲み方だったのかもしれない。しかし、作り手たちが届けたい、その一滴に込められた本来の味わいや香りという「一次情報」は、言葉ではなく、この試飲会場の静かな設えの中にこそ、示されていたのだ。
正解に最も近い場所へ:現場主義のすすめ
では、この情報の海の中で、私たちはどうすれば本質、つまり「正解に最も近い情報」に辿り着けるのだろうか。余市での体験は、私に一つの明確な答えを示してくれた。
それは、「もし時間と機会があるならば、迷わず現場を訪れること」だ。
今回、私が余市蒸溜所という「現場」を訪れたことで得られたのは、単に「水割りは常温の水で」という知識だけではない。歴史ある建物のたたずまい、敷地内に漂う甘く香ばしい香り、そしてウイスキーづくりに込められた人々の情熱。その場の「空気」に込められた、言葉にならないメッセージを読み解こうとすることで初めて、あの琥珀色の一滴が持つ本当の価値と物語を、心から理解することができたのだ。ネットの記事を100本読むよりも、この場所で過ごした数時間の方が、遥かに深く、そして正確に私に本質を教えてくれた。
もちろん、全ての物事において、常に現場を訪れることが可能だとは限らない。時間的な制約、物理的な距離、経済的な問題もあるだろう。そんな時、次善の策として有効なのが、「実際に現場を訪れた人と繋がり、その生の体験談を聞くこと」だと私は思う。現場の空気感を肌で知る人の言葉には、単なるテキスト情報にはない熱量と、ディテールと、文脈が宿っている。その人のフィルターを通して語られるという側面はありますが、少なくとも情報の鮮度と信頼性は、ネット上を漂う不確かな情報とは比較にならない。信頼できる「現場を知る人」を何人持っているか。それが、これからの時代を賢く生き抜くための、一つの重要な資産になるのかもしれない。
結論:正しい情報が、より良い人生を築く
友人との再会とウニ。それが目的だったはずの旅は、思いがけない寄り道によって、予期せぬ宝物を私に与えてくれた。余市蒸溜所での一杯の水割り。それは、私のウイスキーの世界を広げてくれただけでなく、情報というものへの向き合い方を、そしてひいては人生の歩み方をも見つめ直す、貴重なきっかけとなった。
私たちは日々、無数の選択と判断を繰り返しながら生きている。どの仕事を選ぶか、誰と時間を過ごすか、何に価値を見出すか。その一つひとつの判断の質は、その根拠となる情報の質に大きく左右される。不正確な情報や、誰かの受け売りの浅い知識に基づいて下した判断は、時に私たちを望まない方向へと導いてしまうかもしれない。
しかし、自らの足で現場に赴き、自らの五感で本物に触れ、そこで得た確かな情報に基づいて判断を下すならば、その先には、より納得感のある、豊かな人生が待っているのではないだろうか。たとえそれが、今回のように「ついで」や「寄り道」から始まった偶然の発見だったとしても。
北の大地、余市。竹鶴政孝が夢を追い求めたその場所で味わった琥珀色の液体は、私の心に深く、そして温かく染み渡った。もしあなたが今、何かの情報に迷い、判断に確信が持てずにいるのなら。少しだけ勇気を出して、その情報の源泉、その「現場」へと足を運んでみてはいかがだろうか。きっとそこには、画面の向こう側では決して得られない、あなただけの「琥珀色の真実」が待っているはずだ。そしてその真実こそが、あなたのこれからの人生を、より深く、味わい豊かなものへと導いてくれる、最高の羅針盤となるに違いありません。
(ちなみに、この後食べたウニ丼が、感動でより一層美味しく感じられたのは言うまでもありません。)

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役