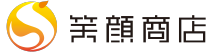はじめに:魂を揺さぶる「100年に1本の芸道映画」との出会い
2025年6月6日の公開以来、異例の大ヒットを記録し、社会現象にまでなっている映画『国宝』。李相日監督が吉田修一の同名小説を映画化したこの作品を、私もついに観覧しました。上映時間175分という長さを全く感じさせない、壮絶な人間ドラマ。観終わった今も、その深い感動と興奮が胸の中で渦巻いています。
何よりもまず、主演の吉沢亮、そして横浜流星が見せた鬼気迫る演技に、終始圧倒されました。特に、任侠の家に生まれながらも歌舞伎界の頂点を目指す主人公・立花喜久雄を演じた吉沢亮。その指先の動き一つ、視線一つに至るまで、稀代の女形としての魂が乗り移ったかのような、まさに「神がかった」としか言いようのない演技でした。
しかし、この映画の魅力は俳優陣の熱演だけに留まりません。主人公・喜久雄の波乱に満ちた人生を通して、本作は私たちに「才能とは何か」「伝統とは何か」、そして「芸の道に生きるとは、どういうことか」という根源的な問いを投げかけてきます。
今回は、この映画『国宝』が描く世界と、そこから私が感じ、考えたことについて、深く掘り下げていきたいと思います。
映画『国宝』とは?壮大な人間ドラマの概要
まずは、この類まれなる作品の基本情報とあらすじを振り返ってみましょう。
・公開日:2025年6月6日
・監督:李相日(『フラガール』『悪人』『怒り』)
・原作:吉田修一
・脚本:奥寺佐渡子
・上映時間:175分(2時間55分)
・制作:CREDEUS(『キングダム』シリーズ等)
・配給:東宝
【あらすじ】
物語の舞台は、華やかさと厳格な伝統が息づく歌舞伎の世界。長崎の任侠の一門に生まれた美貌の少年・喜久雄(吉沢亮)は、父を抗争で亡くし、上方歌舞伎の名門・花井半二郎(渡辺謙)に引き取られます。そこで出会ったのが、半二郎の実子であり、生まれながらのエリートである俊介(横浜流星)。
正反対の血筋と生い立ちを持つ二人は、宿命のライバルとして互いを強烈に意識し、芸の道に青春の全てを捧げます。血筋という越えられない壁、渦巻く嫉妬、そして芽生える友情。歓喜と絶望、信頼と裏切りが交錯する壮絶な50年の一代記を通して、芸の道を極め、孤高の存在「国宝」へと至る男の生き様が描かれます。
【主要キャスト】 この重厚な物語を彩るのは、現在の日本映画界を代表する豪華な俳優陣です。
・立花喜久雄(花井東一郎):吉沢亮
・大垣俊介(花井半弥):横浜流星
・花井半二郎:渡辺謙
・福田春江:高畑充希
・大垣幸子:寺島しのぶ
・小野川万菊:田中泯
・立花権五郎:永瀬正敏
圧倒的な映像美とリアリティが生んだ「社会現象」
本作が単なるヒット作に終わらず、「社会現象」とまで言われる由縁は、その圧倒的なクオリティにあります。
特筆すべきは、吉沢亮と横浜流星が吹き替えなしで挑んだという歌舞伎舞踊のシーンです。四代目中村鴈治郎による徹底した指導のもと、彼らが習得した緻密で繊細な所作は、本物の歌舞伎役者と見紛うほどの完成度。特に、喜久雄が女形として開花していく過程は、俳優・吉沢亮の役者魂そのものがスクリーンに焼き付けられているようで、何度も鳥肌が立ちました。
その本格的な演技を捉えたのが、『アデル、ブルーは熱い色』で知られる世界的撮影監督ソフィアン・エル・ファニのカメラと、『キル・ビル』の美術監督・種田陽平が作り上げた美術です。これまで「禁断の世界」とされてきた歌舞伎の舞台裏や楽屋を、息をのむほど美しく、そして生々しく描き出し、観客を物語の世界へ深く没入させます。
公開当初は週末興行ランキング3位からのスタートでしたが、「3時間が瞬く間に過ぎた」「近年にない衝撃」「吉沢亮の演技が凄まじい」といった絶賛の口コミがSNSなどを通じて爆発的に広がり、2週目には前週比143%という異例の伸びを見せて2位に浮上。公開49日間で興行収入71.7億円、観客動員数510万人を突破するという、まさに伝説的なヒットを記録しています。この熱狂は映画界に留まらず、原作小説が130万部を突破するなど、社会全体で「国宝」への関心が高まっています。
「血」か「実力」か?―そして信じ抜く心の強さ
私がこの映画に強く心を揺さぶられたのは、主人公・喜久雄の壮絶な生き様でした。歌舞伎界という、血筋と家柄が絶対的な価値を持つ世界。そこに任侠の家の息子という「アウトサイダー」として放り込まれた喜久雄は、その才能を認められながらも、世襲制の分厚い壁に何度も阻まれます。
芸を披露する場もなく、日銭を稼ぐために、本物の価値がわからない酒場の客を相手に踊る日々。その姿は、泥水をすするような屈辱の中でも、決して芸を諦めないという執念に満ちていました。
まさに、この喜久雄の姿は、私たちに重要な教訓を教えてくれます。才能や実力があっても、運や環境に恵まれず、それだけではどうしようもない不遇の時期は誰の人生にも訪れます。しかし、そこで腐らずに自分を信じ、技を磨き続ければ、必ず道は開けるのだと。この映画は、その真理を痛切に教えてくれました。この不屈の精神こそが、彼を後の人間国宝という境地へと導いた原動力であることは間違いありません。
そして、彼の生き様を見ながら、私はふと「事業承継」という問題について考えさせられました。血筋を重んじるか、それとも実力を持つ者を選ぶか。これは歌舞伎の世界に限らず、政治や会社組織でも常に経営者を悩ませる重大な問題です。身内びいきが横行し、有能な人材が正当に評価されない組織は、必ず衰退します。世界最古の企業「金剛組」が1400年以上存続してきた秘訣が、血縁よりも実力と徳を重んじることにあったように、組織を永続させるためには実力主義が不可欠なのです。
歌舞伎界の世襲制のリアルと、映画が描く「理想」
では、実際の歌舞伎界の世襲制はどのようになっているのでしょうか。調べてみると、非常に興味深い実態が浮かび上がってきました。
現在も大名跡(だいみょうせき)と呼ばれる偉大な名は、基本的に世襲によって受け継がれています。しかし、それは決して閉鎖的な血縁主義のみで成り立っているわけではありません。才能ある者を外部から受け入れるための「部屋子(へやご)」や「養子」といった、血縁を超えた継承システムが確立されているのです。
このシステムによって頂点に登り詰めた代表的な存在が、人間国宝でもある坂東玉三郎丈です。また、近年大活躍の片岡愛之助丈も、一般家庭の出身から現在の地位を築いています。
映画の主人公・喜久雄のモデルは特定の誰かではなく、架空の人物ですが、そのキャラクターには、こうした「外部から入り、自らの力で道を切り拓いた者」の生き様が色濃く反映されています。「伝えるべきは芸であって、血ではない」―。この考え方が、現在の歌舞伎界にも確かに息づいているのです。
映画『国宝』が本当に伝えたかった核心的メッセージ
李相日監督は、この映画で伝えたかったことについて「役者という生き物の壮絶な生き様、魂そのもの」だと語っています。本作は、歌舞伎という伝統芸能を題材にしながらも、その本質は「何かを極めようとする人間の普遍的な物語」です。
映画の中心にあるのは「血か、芸か」という根源的な問いです。そして、血統を持たないアウトサイダーである喜久雄が持つ、芸の頂点への「渇望」。その渇望こそが、彼を常識の枠を超えた高みへと押し上げる原動力となります。この映画は、私たちに「本物の芸の力」を思い出させてくれます。それは単なる技術の巧みさではありません。人生の全てを懸けて一つの道を追求する人間の魂が放つ輝きであり、それこそが、時代や文化を超えて人の心を動かすのだと。
結論:実力と信念が正当に評価される社会を願って
映画『国宝』は、一人の天才役者の壮絶な一代記であると同時に、現代社会に生きる私たち一人ひとりに対する鋭い問いかけでもあります。
私たちは、血筋や家柄、経歴といった「見かけ」に惑わされず、その人間の持つ本当の実力や情熱を見抜くことができているでしょうか。
『国宝』が描いたのは、芸の道における真剣勝負の世界でした。そして同時に、才能だけでは越えられない壁にぶつかった時、いかに自分を信じ、耐え忍び、努力を続けられるかという、普遍的な人生のテーマでもあります。腐らずに自分を磨き続ければ、必ず誰かが見ていてくれる、道は開ける。この映画は、そんな力強い希望のメッセージを私たちに与えてくれました。
この教えは、社会のあり方にも通じます。私が最も問題だと感じる政治の世界では、能力や志があるわけでもない世襲議員があまりにも多いのではないでしょうか。私たち有権者は、選挙という場で、候補者の背景ではなく実力と政策を厳しく見極め、無能な世襲議員を選ばないという断固たる意志を示す必要があります。
『国宝』が描いたように、出自や血縁に関係なく、真に実力と信念を持った者が正当に評価され、その力を存分に発揮できる社会であってほしい。この映画は、エンターテインメントの枠を超え、そんな切なる願いを私の中に呼び覚ましてくれた、忘れられない一本となりました。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役