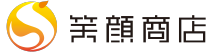プロローグ:雨雲を切り裂いた旅の始まり
旅立ちの朝、スマートフォンの画面が映し出す天気予報は、私たちの心を少しだけ重くさせた。「曇りのち雨」。特に目的地の佐賀県鹿島市周辺は、激しい雨の可能性も示唆されていた。仲間と顔を見合わせ、「どうする?」と短い相談。当初は、博多駅からJR特急に乗り、肥前鹿島駅からは路線バスを乗り継いで各地を巡る、のんびりとした公共交通機関の旅を計画していた。
しかし、この天気だ。バスを待つ時間や、バス停から目的地まで歩くことを考えると、雨に降られるリスクは格段に上がる。「よし、現地でレンタカーを借りよう」。急遽予定を変更し、私たちは博多駅のホームへと向かった。
特急かもめに揺られ、肥前鹿島駅に到着した頃、福岡市内はまだ小雨が降る程度だったという。しかし、鹿島の空は一層暗さを増し、いつ降り出してもおかしくない気配を漂わせていた。予約しておいたレンタカーに乗り込むと、まるでここからが本当の旅の始まりだと告げるように、空気が一層重くなった。
だが、この日の旅が、単なる悪天候との戦いではなく、まるで天が我々のために脚本を書いたかのような、奇跡的な瞬間の連続になるとは、この時の私たちは知る由もなかった。
後から知って驚いたのだが、私たちが最初の目的地である祐徳稲荷神社を出て、昼食へと向かっていたちょうどその頃、福岡市内では1時間に60mmを超える記録的な豪雨に見舞われていたというのだ。
しかし、私たちがいた鹿島の地では、一度として傘を開くことはなかった。
これは、そんな不思議な天運に導かれた、佐賀県鹿島・太良エリアを巡る旅の記録である。そして、その道中で出会った素晴らしい魅力と、だからこそ見えてきた「伸びしろ」についての考察でもある。
第一章:鎮西日光の奇跡 ―― 祐徳稲荷神社、神々の歓迎
私たちの最初の目的地は、日本三大稲荷の一つに数えられる「祐徳稲荷神社」。その絢爛豪華な社殿から「鎮西日光」の異名を持つ、九州屈指のパワースポットだ。
JR肥前鹿島駅でレンタカーを借り、山間の道を進むと、緑の合間から鮮やかな朱色の楼門が姿を現した。空は厚い雲に覆われているにもかかわらず、その色彩は圧倒的な存在感を放っている。貞享4年(1687年)、鹿島藩主鍋島直朝公の夫人、花山院萬子媛が京都から稲荷大神を勧請したのが始まりとされるこの神社は、まさに京都の雅と武家の威厳が融合した美の殿堂だ。
山の斜面に寄り添うように建てられた御本殿は、清水寺の舞台を彷彿とさせる壮麗な懸造り。総漆塗りの極彩色が施された柱や梁は、一つひとつが芸術品であり、職人たちの魂のこもった仕事ぶりに思わず息をのむ。
私たちは、商売繁盛、家運繁栄など、数多のご利益を授かるべく、一段一段、ゆっくりと階段を上り、荘厳な本殿へと向かった。衣食住の神である倉稲魂大神(ウガノミタマノオオカミ)をはじめ、技芸上達の大宮売大神(オオミヤノメノオオカミ)、交通安全の猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)に、静かに手を合わせる。日々の感謝と、これからの事業の成功、そして仲間たちの幸せを祈願した。
その、瞬間だった。
参拝を終え、顔を上げた私たちの目に、信じられない光景が飛び込んできた。今まで空を覆っていた分厚い雲の隙間から、まるでスポットライトのように、一本の強い日差しがまっすぐに社殿へと降り注いだのだ。朱色の社殿が黄金色の光を浴びて、神々しいまでに輝きを増す。それは、まるで神様が「ようこそ」と微笑み、私たちの祈りを聞き届けたと告げてくれているかのような、あまりにも劇的な光景だった。
仲間たちと顔を見合わせ、言葉もなく頷き合う。この奇跡的な光に背中を押されるように、私たちはさらにその先、山頂に鎮座する「奥の院」を目指すことにした。
朱色の鳥居が連なる参道は風情があるが、次第に急な石段へと変わっていく。息を切らしながら一歩一歩、額に汗して登る道中は、確かに少し体力がいる。しかし、登り切った先に待っていたのは、その疲れを瞬時に吹き飛ばすほどの絶景だった。鹿島の町並みと、その先に広がる有明海を一望できるパノラマは、まさに筆舌に尽くしがたい、なんともいえない魅力がある。奥の院で改めて深く手を合わせ、併設された休憩所でしばらく息を整えてから、私たちは達成感と共に山を下り始めた。
天気予報を覆すこの奇跡的な出来事に、私たちはこの旅が特別なものになることを確信した。
第二章:有明海の至宝――多良で味わう竹崎ガニの衝撃
神々しい光に背中を押され、次なる目的地、多良町のカキ小屋へと向かった。有明海の恵みを存分に味わうためだ。お目当ては、この時期に旬を迎えるという「竹崎ガニ」。
カキ小屋の素朴なテーブルにつき、運ばれてきたのは、真っ赤に茹で上がった大ぶりの竹崎ガニだ。甲羅を外すと、中にはオレンジ色の内子と濃厚なカニ味噌がぎっしりと詰まっている。脚の身を丁寧に取り出し口に運ぶと、しっかりとした弾力のある身から、凝縮された甘みと旨味がじゅわっと溢れ出した。
「うまい…!」
思わず声が漏れる。これまで松葉ガニや毛ガニなど、様々なカニを食してきたが、この竹崎ガニの味の濃さは決して引けを取らない。それでいて、価格は1匹2,000円から4,000円程度と、驚くほど手頃なのだ。聞けば、まさに今が旬の走りだという。カキはまだ小ぶりだったが、このカニに出会えただけでも大きな収穫だ。
唯一心残りだったのは、メニューにあった「カニの刺身」を食べ損ねたこと。トロリと甘いであろうその味を想像し、「これは来年、必ず再訪しなければならない」と固く誓った。イカの丸焼きや、磯の香りがたまらないサザエの壺焼きも平らげ、私たちは有明海の豊かな恵みに心から満たされたのだった。
第三章:神秘の鳥居と女人禁制の島――大魚神社と沖ノ島
満腹のお腹を抱え、次に向かったのは「大魚神社」。ここには、有明海の干満差を利用した神秘的な「海中鳥居」がある。私たちが訪れた時は干潮に近く、鳥居の根本まで歩いていけるようだったが、それでもなお、海の中に佇むその姿は幻想的だ。
鳥居のそばにある説明書きに、私の目は釘付けになった。「沖ノ島」という文字。福岡県民にとって「沖ノ島」といえば、世界遺産に登録された宗像の「神宿る島」であり、厳格な女人禁制で知られる場所だ。まさか有明海にも同じ名の島が? 好奇心に駆られ、その場でスマートフォンを取り出し調べてみた。
驚いたことに、この有明海の沖ノ島もまた、伝統的に「女人禁制」が守られている聖地だったのだ。男島と女島からなるこの岩礁は、満潮時には海の中へと姿を消す。約300年前、干ばつに苦しむ村を救うため、「おしま」という娘が人柱となり身を投げたところ、遺体がこの島に流れ着き、恵みの雨が降ったという悲しくも美しい伝説が残っている。以来、島は「おしまさん」として祀られ、五穀豊穣や大漁を祈願する「沖ノ島参り」が今も続けられているという。
海中鳥居は、この聖なる沖ノ島への参道を示すものなのだ。歴史と信仰の深さに、ただの観光スポットではない、人々の祈りが宿る場所なのだと改めて感じ入った。
当日は曇り空で、海の向こうにかすかに見える島影が、おそらく沖ノ島なのだろう。そのぼんやりとした姿が、かえって伝説の神秘性を掻き立てるようだった。周囲には多くの外国人観光客の姿もあり、中にはドローンを飛ばしてこのユニークな景観を撮影している者もいた。古の伝説と現代のテクノロジーが交差する、不思議な空間だった。
第四章:時が止まった町並み――肥前浜宿の光と影
旅の締めくくりに訪れたのは、鹿島市の「重要伝統的建造物群保存地区」、通称「肥前浜宿」だ。ここは、港町として栄えた「浜庄津町浜金屋町地区」と、酒造業で発展した「浜中町八本木宿地区」という、異なる二つの顔を持つ全国的にも珍しい町並みだ。
通称「酒蔵通り」に足を踏み入れると、白壁土蔵の大きな酒蔵や、防火のための「居蔵造」と呼ばれる重厚な町家が連なり、まるで時代劇のセットに迷い込んだかのようだった。芳醇な日本酒の香りがどこからか漂ってくる。しっとりとした空気感と、昔ながらの静かな街並みに、心がじんわりと解きほぐされていくのを感じた。
しかし、その魅力とは裏腹に、私たちの他にはほとんど観光客の姿が見当たらない。この静けさが心地よい一方で、少し寂しくも感じた。
そんな中、一軒の老舗醤油屋の店先で試食を勧められた。少し燻したような独特の風味を持つ醤油は、深いコクがあり非常に美味しい。旅の良い記念になるだろう。そう思い、お土産にしようかと何気なく商品の裏のラベルに目をやった瞬間、私は深くがっかりしてしまった。
原材料名の筆頭に書かれていたのは、昔ながらの丸大豆ではなく、「アミノ酸液」の文字だったのだ。
これは、いわゆる醤油風調味料の主原料として使われるもので、製造工程で塩酸を使って分解するため、発がん性も確認されている「1,3-DCP」や、腎臓への悪影響が懸念される「3-MCPD」といった、クロロプロパノール類が生成されるリスクがある、非常に気にかかる原材料だ。さらに読み進めると、不自然な甘みをつける「果糖ぶどう糖液糖」や、MSG(グルタミン酸ナトリウム)を主成分とする「調味料(アミノ酸等)」といった、気になる文字が並んでいた。
これほど素晴らしい歴史と伝統を持ち、趣のある店構えの老舗なのだから、ぜひとも昔ながらの製法で造られた「本物」で勝負してほしい。コストや生産効率を考えれば、こうした原材料を使わざるを得ない事情があるのかもしれない。しかし、食の安全や本物の味を求める消費者がいることも忘れないでほしい。その土地の風土と職人の技が育んだ、心から安心して使えるものづくりを、こうした老舗にこそ期待してしまうのは、私の我が儘だろうか。
美味しさの裏に隠された現実に、私はこの歴史ある町の「光」と、現代が抱える食の問題という「影」の両面を見た気がした。
エピローグ:鹿島の未来へ――旅の終わりに見えた「伸びしろ」
肥前浜宿を後にし、帰路につくためにレンタカーに乗り込んだ、まさにその時だった。まるで私たちの旅の終わりを待ち構えていたかのように、フロントガラスを叩きつける凄まじい豪雨が降り出したのだ。それは、天が張っていた結界が解かれたかのような、あまりにも見事なタイミングだった。
さらに奇跡は続く。レンタカーを返却するために店に着くと雨は小康状態になり、駅で送迎車を降りる瞬間には再び雨が止んだ。結局、私たちは予報を覆し、一度も雨に濡れることなく旅を終えることができたのだ。
この旅で巡った祐徳稲荷神社、竹崎ガニ、海中鳥居、そして肥前浜宿。一つひとつが個性的で、深い歴史と物語を持つ、一級の観光資源であることは間違いない。祐徳稲荷神社を起点とすれば、磨けばさらに光り輝くポテンシャルに満ち溢れている。
しかし、同時に大きな課題も見えてきた。それは「アクセスの悪さ」だ。今回はレンタカーを利用したからこそ4つの目的地を効率よく回れたが、公共交通機関を使えば、おそらく2か所を巡るのが精一杯だろう。その上、レンタカー屋の数も多いとは言えない。
観光とは、家を出た瞬間から始まる一連の体験だ。移動に疲れ、「もう来なくてもいいかな」と思われてしまえば、リピートは期待できない。
また、鹿島市と太良町といった近隣の市町村が、どう連携しているのかも気になった。わずか数キロしか離れていない場所に、競い合うかのように道の駅が存在する光景は、観光戦略の視点から見れば非効率に映る。個々の「点」がそれぞれに頑張るのではなく、地域全体が「面」となって、訪れる人々をどう楽しませるかという共通の戦略を描く必要があるのではないか。
集客力のあるスポットを中心に、魅力的なストーリーを紡ぎ、ここでしか手に入らないお土産を開発する。そうした一貫性のある取り組みが不可欠だ。観光は、町ぐるみ、地域ぐるみで知恵を絞らなければ、勝ち筋は見えてこない。
天候にまで恵まれた、最高の旅だった。だからこそ、この素晴らしい地域にもっと多くの人に訪れてほしいと心から願う。今回感じた課題は、裏を返せば、この地域には「まだまだ計り知れない伸びしろがある」ということの証明でもある。
奇跡的な天運に導かれた今回の旅は、私に佐賀・鹿島の魅力と共に、地方観光の未来を考える貴重な宿題を与えてくれた。来年、カニの刺身のリベンジを果たすために再訪する時、この町がどんな新しい顔を見せてくれるのか、今から楽しみでならない。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役