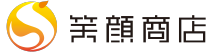先日、ふと思い立って北陸の古都、金沢へと旅に出た。加賀百万石の華やかな文化、美しい街並み、そして新鮮な海の幸。多くの人が金沢に抱くイメージは、きっとそんなところだろう。もちろん私も、その煌びやかな歴史の香りに触れることを楽しみにしていた。
しかし、今回の私の旅の目的は、少しだけ違っていた。私の心を捉えて離さなかったのは、この地に眠るとされる、二つの奇妙で、そしてあまりにも魅力的な物語だった。
一つは、人里離れた森の奥深くに存在する、旧約聖書の預言者モーゼの墓。そしてもう一つは、街の中心に鎮座し、神社の常識を覆す壮麗な門を持つ神社。
古代の壮大な伝説と、明治維新の革新的な精神。一見、何の接点もないように思える二つの場所が、金沢という都市の周辺に存在している。この不思議な符合に導かれるように、私はレンタカーのキーを握りしめ、時空を超える旅へと出発したのだった。
第一章:伝説の森へ – 能登半島に眠るモーゼの謎「モーゼパーク」探訪記
金沢の市街地から車を走らせること約50分。賑やかな観光地の気配は次第に薄れ、車窓の風景は鬱蒼とした緑に覆われていく。目指すは、宝達志水町にある「モーゼパーク」。その名を聞いただけでは、一体どんな場所なのか見当もつかないだろう。しかし、こここそが今回の旅の最初の目的地であり、世界史を揺るがしかねない壮大な伝説の舞台なのである。
カーナビの案内に従い、細い山道へと分け入っていくと、「モーゼパーク」の控えめな看板が見えてきた。駐車場に車を停め、一歩足を踏み入れた瞬間、空気が変わったのを感じた。ひんやりと湿った森の匂い、木々の葉が風にそよぐ音、そしてけたたましいほどの蝉時雨。ここはテーマパークなどではなく、正真正銘、手つかずの自然が広がる「森」そのものだった。
入り口には「クマ出没注意」の看板が物々しく立てかけられている。ひと気のない森の中を一人で歩き始めると、足元では名も知らぬ虫たちが忙しなく動き回り、蜘蛛の巣が顔にかかる。正直なところ、なかなかのスリルだ。だが、この隔絶されたような静けさと緊張感こそが、これから対面する伝説の序章として、ふさわしいのかもしれない。
一体なぜ、日本の能登半島にモーゼの名を冠した公園があるのか。その根拠とされているのが、古神道系の文献『竹内文書』である。歴史学の世界では「偽書」として扱われ、その存在自体がないことにされているこの古文書には、驚くべき記述があるという。
「モーゼはシナイ山に昇った後、天浮船(あまのうきふね)に乗り、能登宝達に着き、『十戒』を授かり三つ子塚に葬られている」
旧約聖書によれば、モーゼは民を率いて約束の地カナンを目前にしながら、その地を踏むことなくネボ山で120年の生涯を終えたとされる。しかし、『竹内文書』は、その後のモーゼの驚くべき旅路を語っているのだ。天浮船――まるで現代のUFOを思わせる乗り物で日本に飛来し、この地で「本当の十戒」を授かり、そして永遠の眠りについたという。
にわかには信じがたい話だが、ロマンがある。そんな思いを胸に、私は森の中に続く「ロマンの小路」と名付けられた遊歩道を進んだ。木漏れ日が優しく差し込む小径を抜けると、少し開けた場所にたどり着く。「ミステリーヤード」と名付けられたそのエリアからは、木々の向こうにこんもりとした3つの丘を見渡すことができた。
あれが、「三ツ子塚古墳群」。5世紀から6世紀にかけて造られたとされる実際の古墳群であり、伝説では、あの中の一つがモーゼの墓なのだという。静まり返った森の中で、古代の墳墓と旧約聖書の預言者が結びつく。その光景は、どこか非現実的で、荘厳でさえあった。
この公園が生まれた背景もまた興味深い。モーゼパークがオープンしたのは1993年。もともと大きな産業や観光資源に恵まれなかった旧押水町(現・宝達志水町)が、地元在住の山根キクという女性が所有していた『竹内文書』の記述と、モーゼの墓の存在を主張したことをきっかけに、町おこしの一環として約1億5千万円もの予算を投じて整備したのだという。壮大な古代の伝説が、現代の地域振興という極めて現実的な課題と結びついて生まれた場所。そのギャップもまた、この公園の持つ不思議な魅力の一つだろう。
そもそもモーゼとは、いかなる人物だったのか。ヘブライ語で「モーシェ」と呼ばれる彼は、旧約聖書の『出エジプト記』の中心人物だ。紀元前13世紀頃、エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民を率いて脱出し、40年にわたる荒野の旅の末、彼らを約束の地へと導いた偉大な指導者。シナイ山で神から「十戒」を授かった預言者として、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という世界の三大宗教すべてにおいて、極めて重要な存在とされている。
彼の業績は、現代社会にも計り知れない影響を与え続けている。「汝、殺すなかれ」「汝、盗むなかれ」といった十戒の教えは、西洋文明における法制度の根幹をなし、奴隷解放の物語は、後の人権運動にも大きなインスピレーションを与えた。モーゼは単なる宗教家ではなく、法律家であり、政治家であり、軍事指導者でもあった。人類史上、最も影響力のある人物の一人と言っても過言ではない。
そんな世界的偉人が、なぜ日本の片田舎に?――森の中で古墳を眺めながら、私は改めてその問いに立ち返る。真実かどうかを問うのは、もはや野暮なのかもしれない。科学や歴史考証のメスを入れれば、この伝説は脆くも崩れ去るだろう。しかし、古代の人々が何を信じ、何を語り継いできたのか。そして、その伝説に一縷の望みを託し、未来を切り開こうとした現代の人々の想い。この森に満ちているのは、そうした人間の想像力と、時を超えて何かを信じようとする切ないほどの願いなのではないか。
モーゼパーク。そこは、信じる者にとっては聖地であり、疑う者にとっては単なる森と古墳群かもしれない。だが、訪れる者すべてに、古代への尽きせぬロマンと、歴史の「もしも」を夢想する楽しみを与えてくれる、不思議な力に満ちた場所だった。
第二章:和洋の奇跡 – 尾山神社のステンドグラスに度肝を抜かれる
モーゼの眠る伝説の森を後にし、再び金沢市街へと車を走らせた。古代のロマンに浸った頭を現実に戻し、次に向かったのは、加賀百万石の歴史の中心地ともいえる場所、「尾山神社」だ。
兼六園や金沢城公園からも、ほど近いこの神社は、加賀藩祖・前田利家公と、その正室であるお松の方を祀る、由緒正しい神社である。戦国の世を駆け抜け、「槍の又左」の異名で恐れられた猛将・利家公。その偉業を偲ぶ場所にふさわしく、境内は厳かな空気に包まれている…はずだった。
神社の入り口にたどり着いた私は、自分の目を疑った。目の前にそびえ立つ神門を見て、思わず声が漏れる。
「なんだ、これは……?」
一階部分は、紛れもなく日本の城郭を思わせる重厚な石垣造り。しかし、その上にそびえる三階建ての楼門は、どう見ても日本の神社の様式ではない。特に最上層、三階部分にはめ込まれているのは、色とりどりのガラス。――そう、ステンドグラスだ。
なぜ、神社の門の上に、教会で見るような洋風の建造物が乗っているのか。こんな神社、生まれて初めて見た。
一瞬、頭に浮かんだのは日光東照宮だった。あそこも徳川家の威光を示すため、中国風の豪華絢爛な装飾がふんだんに取り入れられている。しかし、これは「中華風」ではない。明らかに「欧風」だ。その大胆で奇抜な組み合わせに、私は完全に度肝を抜かれてしまった。
あまりの衝撃に、その場でスマートフォンを取り出し、尾山神社について調べてみる。すると、この奇妙な門の謎が次々と明らかになっていった。
この神門が建てられたのは、明治8年(1875年)。神社そのものの創建が明治6年(1873年)だから、まさしく文明開化の真っ只中に生み出された建築物だ。設計したのは、オランダ人のホルトマン。彼は医学の教師として金沢に招かれた人物だったという。
この門は、和・漢・洋の三様式を巧みに混用した、全国的にも極めて珍しい建築物として、国の重要文化財に指定されている。 一階部分は、戸室石(とむろいし)という地元産の石材を使った和風の城郭様式。 二階部分は、唐破風(からはふ)を持つ中華風。 そして三階部分が、四面五彩のギヤマン(ステンドグラス)が輝く西洋風。 さらに驚くべきことに、屋根の上には日本最古とされる避雷針まで設置されているという。
このステンドグラスは、単なる装飾ではなかった。かつては内部で灯りが灯され、「御神灯」として金沢の街を優しく照らしていた。その光は遠く日本海まで届き、航行する船の目標、つまり灯台の役割まで果たしていたというのだから、二度驚かされる。
明治という新しい時代の幕開けに、旧加賀藩の精神的支柱として創建された神社。そのシンボルである神門に、これほど斬新で先進的なデザインを取り入れた金沢の人々の気概は、一体どれほどのものだったのだろうか。伝統を重んじながらも、新しい文化を恐れず、大胆に取り入れていく。まさに「加賀百万石」のプライドと革新性を見せつけられたような気がした。
門をくぐり境内へ進むと、そこには落ち着いた佇まいの拝殿や本殿が鎮座していた。前田利家公の勇壮な銅像や、才能豊かだったというお松の方の像が、訪れる人々を静かに見守っている。旧金沢城の二の丸から移築されたという豪華な東神門や、雅な楽器を模して造られた美しい庭園「神苑」など、見どころは尽きない。
しかし、やはり私の心に最も強く焼き付いたのは、あの神門の姿だった。日没後にはライトアップされ、ステンドグラスが内側から幻想的な光を放つという。その光景は、さぞかし美しいことだろう。
調べてみると、尾山神社のように伝統的な神社建築にステンドグラスを融合させた例は、日本国内では他に類を見ない、実質的に唯一無二の存在であることがわかった。仏教寺院や教会で和洋折衷の建築が見られることはあっても、神道の神社でこれほど大胆な試みが行われたのは、後にも先にもここだけなのだ。
尾山神社は、単に珍しい建築物というだけではない。それは、明治という激動の時代を生きた金沢の人々の、未来への希望とエネルギーの結晶そのものなのだ。
第三章:異文化融合の社 – 日本の神社建築に見る寛容性
尾山神社で受けた衝撃は、私にある探求心をもたらした。日本の神社建築は、どれほど異文化に対して開かれてきたのだろうか。尾山神社が「和洋折衷」の極めて稀な例であるならば、比較対象として挙げた日光東照宮のような「和漢折衷」の神社は、他にどれくらい存在するのだろうか。
まず、日光東照宮(栃木県)について改めて考えてみる。1636年、三代将軍・徳川家光によって現在の姿に造営されたこの神社は、徳川幕府の権威を天下に示すための装置でもあった。その象徴が、一日中見ていても飽きないことから「日暮御門」とも呼ばれる陽明門だ。500を超える極彩色の彫刻には、龍や鳳凰、唐獅子といった中国由来の霊獣や、孔子や老子など中国の故事に由来する人物像がこれでもかとばかりに盛り込まれている。これは、当時の東アジアにおける文化的中心地であった中国の様式を取り入れることで、徳川の権威を絶対的なものとして見せつける、という明確な政治的意図があった。
尾山神社と日光東照宮。両者は伝統的な神社建築に異文化の要素を大胆に取り入れたという点で共通している。しかし、その背景は大きく異なる。
・日光東照宮:江戸時代初期、中華文明の権威を借りて幕府の威光を示すという政治的メッセージが込められた「和漢折衷」。
・尾山神社:明治時代初期、西洋文化への憧れと文明開化の精神を体現するという時代の空気を反映した「和洋折衷」。
では、日光東照宮のような中華風の意匠を取り入れた神社は、他にどのようなものがあるのか。調べてみると、数は多くないものの、各地に興味深い例が存在することがわかった。
[1] 北野天満宮(京都府):豊臣秀頼によって1607年に造営された社殿は、桃山文化の豪華絢爛さを象徴する。中国風の曲線を持つ唐破風や、龍・鳳凰などの極彩色彫刻は、まさに和漢融合の美しさだ。
[2] 春日大社(奈良県):鮮やかな朱色で統一された社殿群は、古代から続く中国文化への敬意を表している。朱色は中国で神聖な色とされており、その色彩感覚に大陸の影響が見て取れる。
[3] 豊国神社(京都府):豊臣秀吉を祀るこの神社もまた、北野天満宮と同様、桃山文化の華やかさを伝える。唐門の彫刻など、随所に中華風のモチーフが用いられている。
[4] 伏見稲荷大社(京都府):有名な千本鳥居の朱色もまた、中国文化における神聖で縁起の良い色としての意味合いを持つ。その圧倒的な景観は、日本の美意識と大陸の色彩感覚が融合した稀有な例と言えるだろう。
これらの神社は、飛鳥・奈良時代から続く大陸文化への憧憬や、安土桃山時代の権力者による威光の誇示、仏教や儒教といった思想の影響など、それぞれの時代背景の中で中華風の要素を取り入れてきた。
こうして見ると、日本の神道、そして神社建築がいかに柔軟で、寛容であったかがよくわかる。神道は、古来からの自然崇拝を基盤としながらも、外来の仏教や儒教の思想を巧みに取り込み、神仏習合という独自の信仰形態を生み出してきた。その精神は建築にも表れているのだ。
異文化をただ模倣するのではない。自らの伝統と融合させ、全く新しい独自の美を創造する。尾山神社のステンドグラスも、日光東照宮の彫刻群も、その精神性の見事な発露なのだ。それは、日本の文化が持つ、最も誇るべき特質の一つと言えるのかもしれない。
終章:伝説と革新が息づく街、金沢で思うこと
能登の森にひっそりと眠る古代預言者の伝説。そして、明治の光を今に伝える革新的な神門。 今回の金沢の旅は、私の心を大きく揺さぶるものとなった。
世界史の常識を覆すモーゼパークの壮大な物語は、真偽を超えて、古代のロマンに思いを馳せることの楽しさを教えてくれた。歴史とは、勝者が記した一つのシナリオに過ぎないのかもしれない。その裏には、語られることのなかった無数の「もしも」が隠されている。そんな歴史の奥深さに触れたような気がした。
一方、尾山神社が見せてくれたのは、過去の伝統に安住することなく、未来を見据えて新しい文化を大胆に取り入れた、明治の人々の力強い精神だった。和漢洋が渾然一体となったあの神門は、日本の近代化が、単なる西洋の模倣ではなく、自らの文化を土台とした創造的な営みであったことを雄弁に物語っている。
伝説と革新。 この二つの物語を巡る旅を終えて、私は金沢という街が持つ、底知れない魅力を改めて感じていた。それは、古いものを大切に守りながらも、常に新しいものを受け入れ、自らの血肉としてきた懐の深さだ。古代の伝説が現代の町おこしに繋がり、明治の先進性が今なお観光客を魅了する。この街には、過去から未来へと続く、しなやかで力強い時間が流れている。
もしあなたが金沢を訪れる機会があるならば、美しい茶屋街や庭園を散策するだけでなく、ほんの少し足を延ばし、あるいは視点を変えて、この街に息づく時空を超えた物語に耳を傾けてみてはいかがだろうか。
きっとそこには、あなたの知らない金沢の、そして日本の新たな顔が待っているはずだ。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役