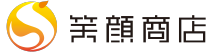はじめに:一本の電話が運んできた熱狂
それは、蒸し暑さが少し和らいできた、ある日の午後のことでした。鳴り響いたスマートフォンの画面に表示されたのは、長年コンサルティングでお付き合いのあるクライアントの社長の名前。何かトラブルだろうか、一瞬の緊張と共に通話ボタンを押した私の耳に飛び込んできたのは、普段は冷静沈着な社長の、上ずった、それでいて紛れもない歓喜の声でした。
「やりました!うちのメニューが、あの藤井聡太竜王・名人の『勝負めし』に選ばれました!」
「それはよかった。おめでとうございます!」 将棋界の最高峰、八大タイトルを独占し、その一挙手一投足が国民的な関心事となる藤井聡太竜王・名人。彼が重要な対局の昼食に選ぶ「勝負めし」は、単なる食事ではありません。それは、勝敗の行方を占うゲン担ぎであり、ファンにとっては棋士の心理やコンディションを読み解くヒントであり、そして何よりも、選ばれた店や地域にとっては、計り知れない経済効果と名誉をもたらす「現代の打ち出の小槌」のような存在です。
対局地の自治体が威信をかけて公募する「勝負めし」。クライアントがその候補に応募し、一次審査を通過したことは聞いていました。しかし、数多の競合の中から、あの藤井竜王・名人の眼鏡にかなうというのは、まさに天文学的な確率です。電話口の向こうで、社長が「信じられない」と繰り返す気持ちが痛いほどわかりました。
この一本の電話を境に、クライアントの店は熱狂の渦に巻き込まれます。テレビ局の取材クルーが店の前に列をなし、新聞記者の電話は鳴り止まず、SNSでは「聖地巡礼」を誓う将棋ファンの投稿が飛び交いました。もちろん、客足は爆発的に増加し、藤井竜王・名人が注文したそのメニューは、仕込みがまったく追いつかないほどの注文殺到。地域全体が、まるで祝祭のような活気に包まれたのです。
この出来事を目の当たりにし、私の脳裏には数年前の記憶が鮮やかに蘇っていました。そして、SNSが情報インフラの主役となったこの時代においても、決して色褪せることのない、ある巨大な力の存在を改めて痛感させられたのです。そう、「マスコミの力」です。
第一部:マスコミがもたらす光 ― スポットライトが奇跡を生むとき
マスメディアが持つ影響力は、時として私たちの想像を遥かに超えるポジティブなエネルギーを生み出します。それは、埋もれていた価値に光を当て、人々の心を動かし、経済を活性化させる力です。私の経験した二つの出来事は、その「光」の側面を象徴するものでした。
第1章:藤井聡太と「勝負めし」現象という名の社会現象
そもそも、なぜ一人の棋士の食事が、これほどまでに社会的な関心事となるのでしょうか。
将棋の対局は、時に十数時間にも及ぶ、極度の集中力と精神力を要求される知的格闘技です。棋士たちは、その膨大なエネルギーを補給するために食事をとります。かつては、出前で済ませたり、簡素なもので済ませたりすることが多かったようですが、将棋がエンターテインメントとして広く楽しまれるようになるにつれ、対局中の食事もまた、ファンが観戦を楽しむための一つの要素として注目されるようになりました。
特に、藤井聡太竜王・名人の登場は、その流れを決定的なものにしました。彼の圧倒的な強さと謙虚な人柄は、「観る将」と呼ばれる新たなファン層を爆発的に増加させました。ファンは、彼の思考の深さだけでなく、対局中に見せる人間的な側面に魅了され、その一つが「食事」や「おやつ」だったのです。彼が「おいしい」と口にしたものは、翌日には市場から姿を消す。その影響力は、もはや一人の棋士の枠を超え、トップインフルエンサーのそれに匹敵します。
今回のクライアントのケースは、まさにその現象の渦中に飛び込んだ形でした。選ばれたメニューは、地元の新鮮な食材をふんだんに使い、店主が長年かけて完成させた自信作。しかし、それはあくまで「知る人ぞ知る」一品でした。それが、藤井竜王・名人が選んだという事実、そしてその事実をマスコミが一斉に報じたことで、物語は一変します。
報道後の店の様子は、まさに「戦場」だったと社長は語ります。開店前から数十人の行列ができ、電話は一日中鳴りっぱなし。SNSには、実際に食べた人々の感動のコメントが溢れ、「#藤井聡太」「#勝負めし」のハッシュタグと共に拡散されていきました。その経済効果は、一店舗に留まりません。遠方から訪れた客が地域の他の店で買い物をし、宿泊施設を利用することで、地域経済全体が潤い始めました。マスコミの一報が、地域活性化の起爆剤となったのです。これは、マスコミが持つ「価値の発見と増幅」という機能が、最も幸福な形で発揮された事例と言えるでしょう。
第2章:テレビが起こした40,000食の奇跡
マスコミの光が奇跡を起こした経験は、これだけではありません。数年前、それは日本中が新型コロナウイルスの暗いトンネルの中にいた時のことです。
飲食業界は、未曾有の危機に瀕していました。緊急事態宣言、外出自粛、時短営業。私のクライアントである、ある食品通販会社も例外ではなく、売上は激減し、先行きの見えない不安に誰もが押しつぶされそうになっていました。
そんな八方塞がりの状況の中、藁にもすがる思いで応募した、朝の人気情報番組のプレゼント企画に、クライアントの商品が採用されたのです。それは、本当に小さな、数分間のコーナーでした。しかし、その数分間が、会社の運命を劇的に変えることになります。
番組の司会を務める、国民的な人気女優。彼女が商品を試食した瞬間、スタジオの空気が変わりました。一口食べた彼女の目が輝き、「美味しい!」という一言。そして、台本にはなかったであろう「もう一杯、お代わりいいですか?」という言葉が続いたのです。
その瞬間から、奇跡は始まりました。
放送直後、会社の電話回線は完全にパンク。通販サイトにはアクセスが殺到し、数分でサーバーがダウンしました。復旧しても、数秒おきに注文が入る異常事態。従業員総出で対応しても、まったく追いつきません。
最終的に、その商品は、わずか数日で40,000食という、会社の創業以来、記録的な売り上げを達成したのです。
あの時の社長の喜びは、単なる喜びだけではなかったと思います。それは、自分たちの作ってきたものが認められたという誇り、そして、暗闇の中に差し込んだ一筋の光に対する、心からの感謝の姿でした。一人の人気女優の「お代わり」という純粋な一言。それを、テレビという巨大な拡声器が日本中のお茶の間に届けたことで、一つの会社が救われたのです。これもまた、マスコミの力がもたらした、紛れもない「光」でした。
第二部:なぜマスコミは今なお強いのか? ― 憧れと影響力の源泉
SNSの台頭により、誰もが情報発信者になれる時代。「マスコミは終わった」という声も聞かれるようになりました。しかし、本当にそうでしょうか。前述の二つの事例は、その影響力が決して衰えていないことを雄弁に物語っています。では、その力の源泉はどこにあるのでしょうか。
それは、「信頼性」と「リーチ力」という、古くて新しい価値にあると私は考えます。SNSの情報は、速報性と拡散力に優れる一方で、その真偽は玉石混交です。フェイクニュースや誤情報が溢れる中で、多くの人々は無意識のうちに「裏付けのある情報」を求めています。新聞社やテレビ局といった組織が、編集や校閲というプロセスを経て発信する情報には、依然として一定の「信頼性」や「権威性」が宿っているのです。
そして、何よりもテレビが持つ「リーチ力」。特定のコミュニティに閉じるSNSとは異なり、テレビはお茶の間という不特定多数に、同時に情報を届けることができます。デジタルデバイドに関わらず、高齢者から子供まで、幅広い層に訴えかける力は、他のメディアの追随を許しません。
この「信頼性」と「リーチ力」に、「有名人」という触媒が加わった時、その影響力は化学反応を起こし、爆発的に増大します。藤井聡太竜王・名人という現代のヒーロー。国民的人気女優という憧れの存在。彼らの言動は、マスメディアという公の舞台で語られることで、単なる個人の感想を超え、社会的な「お墨付き」としての価値を帯びるのです。
この強大な影響力は、多くの若者を惹きつけます。社会に大きなインパクトを与えたい、世の中を動かす仕事がしたい。そんな純粋な動機から、マスコミ業界の門を叩く人々は後を絶ちません。それは、人々に希望や感動を与えることができる、素晴らしい仕事であることに疑いの余地はありません。しかし、その力の裏側には、光が強ければ強いほど濃くなる、深い「影」もまた存在することを、私たちは忘れてはならないのです。
第三部:マスコミが抱える影 ― 凶器と化すペンとカメラ
強大な力は、常に危険を伴います。使い方を誤れば、それは多くの人を救う光から、多くの人を傷つける凶器へと姿を変えます。
ある日突然、事実無根の疑惑を報じられ、社会的信用を失墜させられた経営者。過熱する取材競争の中でプライバシーを暴かれ、平穏な日常を奪われた一般人。些細な失言を切り取られ、全国的な非難の的となった著名人。マスコミによる「言葉の暴力」によって、人生を狂わされた人々の例は枚挙にいとまがありません。
なぜ、このような悲劇が繰り返されるのでしょうか。
その背景には、視聴率や販売部数を追い求めるあまり、情報の正確性や人権への配慮が二の次にされるという、メディア業界の構造的な問題があります。よりセンセーショナルな見出し、より衝撃的な映像が求められ、その競争の中で、裏付け取材は疎かになり、一方的な視点からの報道がまかり通ってしまう。
それは、現場で働く記者個人の勉強不足や倫理観の欠如なのでしょうか。それとも、広告収入に依存し、権力やスポンサーの意向に忖度せざるを得ない、「お金」の問題なのでしょうか。おそらく、その両方なのでしょう。
一度発信された情報は、デジタルの海に残り続け、たとえ後で訂正記事が出されたとしても、最初に与えた負のイメージを完全に払拭することは極めて困難です。そのペン先やカメラは、人の人生を、そして時には命さえも奪いかねないほどの力を持っている。その自覚と覚悟が、果たして今のマスコミにどれほどあるのか、私は時々、強い疑問を感じずにはいられません。
結論:両刃の剣を、私たちはどう使いこなすのか
藤井竜王・名人の「勝負めし」に選ばれたクライアントは、今も幸福な熱狂の中にいます。コロナ禍で奇跡の復活を遂げたクライアントは、あの日の感謝を忘れずに事業を続けています。これらは、マスコミの力がもたらした、紛れもない「光」の物語です。
しかし、その強烈な光を体験したからこそ、私はその裏側にある影の存在を、より一層強く意識するようになりました。マスコミの力は、まさしく「両刃の剣」です。それは社会を豊かにする原動力にもなれば、人々を奈落の底に突き落とす凶器にもなり得ます。
大切なのは、作り手と受け手、双方がその力を正しく理解し、向き合うことではないでしょうか。
作り手側には、その影響力に対する徹底した自覚と、何よりも人としての倫理観が求められます。ペンやカメラの先にいるのが、血の通った人間であることを決して忘れてはならない。
そして、私たち情報の受け手にもまた、責任があります。一つの情報を鵜呑みにせず、複数の情報源を比較検討する。報道の裏にある意図や背景を読み解こうと努める。そして、SNSなどで安易に情報を拡散し、誰かを傷つける側に加担しない。そうしたメディア・リテラシーを身につけることが、これまで以上に重要になっています。
マスコミという強大な力。その光を最大限に享受し、その影を最小限に抑える社会。それは、メディアに関わる全ての人間の、不断の努力によってのみ実現されるのだと、私は信じています。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役