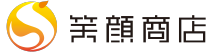石川県、金沢。この街の名を口にすれば、多くの食通たちの脳裏に、新鮮な海の幸が煌めく寿司や、濃厚な旨味を湛えた高級魚「のどぐろ」、そして独自の進化を遂げた「金沢カレー」といった、きら星のごとき名物グルメが浮かび上がるだろう。北陸の豊かな自然と、加賀百万石の歴史が育んだその食文化は、訪れる者を決して飽きさせない奥深さを持っている。
私もまた、そんな王道の美味を求めて金沢の地に降り立った一人だった。しかし、旅とは常に予定調和を裏切る発見に満ちている。今回、私の心を最も強く揺さぶったのは、そうした誰もが知る名物ではなかった。それは、カツ丼の概念そのものを覆す一皿と、一度聞いたら忘れられない強烈な名前を持つ、斬新な土産物との出会いであった。
本記事は、単なるグルメレポートではない。金沢という土地が持つ、伝統を守りながらも常に新しい価値を創造しようとする「温故知新」の精神を、食というフィルターを通して紐解く探訪記である。さあ、常識を軽やかに飛び越える、金沢の食の世界へご案内しよう。
第一章:新星現る!金沢駅で出会った「閉じないカツ丼」の衝撃
旅の玄関口、金沢駅。多くの人で賑わう駅ビル「あんと」の一角に、私の旅の価値観を揺るがす店はあった。その名は「金沢かつぞう」。能登豚をメインとしたとんかつ専門店で、地元で絶大な人気を誇る「金沢まいもん寿司」グループが手掛ける系列店だという。それだけで、素材へのこだわりと味への期待は高まる。
私の目当ては、この金沢駅あんと店でのみ提供されるという限定メニュー、「金沢カツ丼」。SNSで話題となり、実に月間650食以上も出るという驚異的な人気メニューだ。席に着き、逸る心を抑えながら待っていると、やがて運ばれてきたその一皿は、私の知る「カツ丼」の姿とは全く異なっていた。
一杯に込められた「金沢ブランド」の共演
目の前にあるのは、一般的なカツ丼のように、とんかつがふんわりとした卵でとじられている、あの牧歌的な風景ではない。
釜炊きでつやつやと輝く石川県産オリジナルブレンド米のご飯。その上には、とろりとした特製の「あんかけ」が敷かれ、主役である分厚い能登豚のとんかつが堂々と鎮座している。そして、その中央には、まるで満月のように鮮やかな黄身を持つ「生卵」が、ぷるんと盛り付けられているのだ。そう、これこそが「閉じないカツ丼」と呼ばれる所以。卵で“とじない”ことで、とんかつ衣のサクサク感と、半熟卵のとろりとした食感を、同時に、そして最高の状態で味わえるという革新的なスタイルなのである。
おすすめの食べ方に従い、まずは一切れのとんかつを、添えられた「能登の塩」でいただく。カリッとした衣の食感の直後、能登豚のきめ細やかな肉質から、じゅわっと上品な脂の甘みが溢れ出す。臭みは一切なく、ただただ純粋な豚肉の旨味が口の中を満たす。素材への絶対的な自信がなければ、この食べ方は提案できないだろう。
次に、店特製の「魚醤入りとんかつソース」をかけてみる。一般的なソースの甘酸っぱさに加え、魚醤由来の奥深いコクと香りが、能登豚の旨味をさらに立体的に引き立てる。これだけでご飯が何杯でもいけてしまいそうだ。
そして、いよいよ真骨頂。生卵を崩し、あんかけ、ご飯、とんかつを大胆に混ぜ合わせる。この瞬間、全てのパーツが一体となり、全く新しい料理が完成する。まろやかな卵黄が、出汁の効いた優しい味わいのあんかけと絡み合い、サクサクのとんかつを優しく包み込む。それは、親子丼のようでもあり、天津飯のようでもあり、しかし、そのどれでもない、紛れもない「金沢カツ丼」という名の、唯一無二の美食体験だった。
この一杯の感動は、主役の能登豚だけで成り立っているわけではない。脇を固める役者たちの質の高さが、このカツ丼を特別なものに昇華させているのだ。
あんかけの出汁に使われているのは、金沢の老舗「直江醤油」。その名を聞いて、歴史ファンならピンとくるかもしれない。「まさか、あの名将・直江兼続の子孫が?」そんなロマンに想いを馳せながら味わう醤油は、また格別だ。さらに、味の決め手となるみりんは、なんと創業寛永二年(1625年)という、300年以上の歴史を誇る老舗中の老舗「福光屋」のもの。天然素材にこだわり抜いて作られたそのみりんが、品の良い甘みとコクを生み出している。
そして、この美食体験を完成させる最後のピースが「器」。地元の陶芸家が焼き上げたという器は、温かみのある手触りで、料理を一層引き立てる。主役の食材から調味料、そして舞台となる器に至るまで、全てが石川・金沢の選りすぐりの逸品。まさに、地域の力が結集した「オール金沢」の一杯。このコラボレーションこそが、単なる珍しいカツ丼で終わらない、圧倒的なブランド価値を生み出しているのだと、私は深く納得した。
第二章:歴史が息づく、金沢の個性派カツ丼文化を探る
「金沢かつぞう」の革新的な一杯に衝撃を受けた私は、この街のカツ丼文化のルーツや、他にもユニークなものが存在しないか、さらに深掘りして調べてみることにした。すると、まるで金沢の歴史を映し出すかのような、驚くほど個性的で物語のあるカツ丼が、この地で長く愛され続けていることがわかってきたのだ。今回は時間の都合で実食は叶わなかったが、その魅力的な姿は、次回の旅への宿題として、私の心を強く惹きつけている。
芸妓が愛した裏メニュー「自由軒の昔のカツ丼」
まず、私の探究心をくすぐったのが、ひがし茶屋街に佇む1909年(明治42年)創業の老舗洋食店「自由軒」にあるという、「昔のカツ丼(むかカツ)」だ。調べてみると、もともとは茶屋で働く芸妓さんのリクエストから生まれた裏メニューだったというから、その成り立ちからして興味深い。
そのビジュアルは驚くべきもので、ご飯の上に乗っているのは豚肉ではなく「牛ヒレカツ」。そして、そのカツを覆い隠すように、大量の「茹でたキャベツ」と「生のきゅうり」がこんもりと盛られているそうだ。何より衝撃的なのは、このカツ丼には出汁やタレといった味付けが一切なされていないこと。食べる人がテーブルに置かれたウスターソースや塩、胡椒を使い、自分好みの味を完成させるという、究極のカスタマイズスタイルらしい。
なぜこのような形になったのか。その背景には、美意識の高い芸妓さんたちの「自分好みの味付けで、さっぱりと食べたい」「野菜もたくさん摂りたい」という願いがあったという。ビフカツが主流だった時代、美を追求する彼女たちのニーズに応える形で生まれたこの一皿は、まさに金沢の華やかな茶屋文化の産物。歴史の物語を味わうような、知的な魅力に満ちたカツ丼だ。
昭和のノスタルジー「グリル中村屋の皿カツ丼」
さらに調べていくと、1938年(昭和13年)創業の「グリル中村屋」にも、「皿カツ丼」というユニークな名物があることがわかった。その名の通り、丼ではなく深めの皿で提供され、とんかつの上には、まるでカレーのようにとろりとした「玉子入りあんかけ」がたっぷりとかかっているという。付け合わせの千切りキャベツとナポリタンスパゲティが、昭和の洋食店らしいノスタルジーを誘う。
写真で見るその姿は、心温まるビジュアルだ。和風出汁をベースにした甘辛いあんかけが、サクサクのとんかつと熱々のご飯に絡む光景を想像するだけで、お腹が空いてくる。長年、金沢市民の胃袋を支えてきたであろう、その優しくも奥深い味わいを、いつか必ず体験してみたい。
これら個性的なカツ丼の存在は、金沢という街の懐の深さを物語っている。自由軒の一皿は金沢の茶屋文化を、中村屋の一皿は昭和の洋食文化を、それぞれ色濃く映し出す鏡のような存在だ。人々は伝統を重んじながらも、外部の文化を柔軟に受け入れ、自分たちのものとして昇華させてきた。カツ丼というありふれた料理にさえ、これほどの多様性と物語性が生まれるのは、まさにその証左と言えるだろう。
第三章:伝統と革新の融合が生んだ、衝撃の土産物「バターの乱」
金沢の食の奥深さにすっかり魅了された私は、旅の締めくくりに、この感動を持ち帰るべく土産物探しを始めた。そこで出会ったのが、私の旅の記憶に、カツ丼と並んで鮮烈な印象を刻みつけることになった逸品である。
その名は、「能登柿之助 バターの乱」。
なんと強烈なインパクトを持つネーミングだろうか。歴史物語の一場面を切り取ったかのような、勇壮で少し不穏な響き。一体、どんな商品なのか。興味を惹かれ手に取ってみると、それは金沢市の老舗青果店「サカイダフルーツ」が手掛ける、革新的な干し柿スイーツだった。「石川ブランド製品認定制度」のグッド石川ブランドにも認定されているというから、その品質は折り紙付きだ。
商品は、能登地方の志賀町で、手塩にかけて作られた最高級の干し柿「ころ柿」の中心に、スライスした極上のバターを大胆にサンドしたもの。和の食材の代表格である干し柿に、洋の象徴であるバターを組み合わせる。まさに、伝統と革新の「乱」である。
驚くべきは、この組み合わせが、全くの奇をてらったものではないという点だ。実は、石川県の和食料理人の間では、古くから「ころ柿とバター」は「至福の味」として知られ、正月のおせち料理などにも使われる、知る人ぞ知る季節の逸品だったという。料理人たちの間で秘伝のように語り継がれてきた、その禁断の味を、誰もが楽しめるように初めて商品化したのが、この「バターの乱」なのだ。
冷凍で販売されているため、半解凍の状態でいただくのがおすすめだという。口に運ぶと、まず、ねっとりとした干し柿の濃厚な甘みが広がる。能登でしか栽培されていないという「最勝柿」を使い、一つひとつ手作業で作られたころ柿は、まるで天然の和菓子のようだ。そして、その甘みを追いかけるように、ひんやりとしたバターが舌の上でゆっくりと溶け始める。ミルキーなコクと、ほのかな塩気が、干し柿の甘さと見事に融合し、これまでに経験したことのない、甘美で複雑な味わいを生み出す。
これは、スイーツという言葉だけでは表現しきれない、一つの完成された料理だ。ワインや日本酒との相性も抜群だろう。
商品名である「バターの乱」は、単に和と洋の組み合わせというだけでなく、伝統の世界に斬り込み、新たな価値を創造するという、作り手の革命的な意志の表れなのかもしれない。冷凍加工技術によって、かつては冬季限定だった「ころ柿」の味を一年中楽しめるようにした工夫も、伝統の継承と発展に対する真摯な姿勢の表れだ。
結論:金沢の食文化に学ぶ「温故知新」の精神
今回の金沢の旅は、私の食に対する価値観を大きく広げてくれるものとなった。
新しい素材の組み合わせと提供方法で、カツ丼界に新風を吹き込む「金沢かつぞう」。調査によってその存在を知った、茶屋文化や洋食の歴史を背景に持つ「自由軒」と「グリル中村屋」。そして、料理人の間で密やかに楽しまれていた伝統の味を掘り起こし、斬新なネーミングとアイデアで現代に蘇らせた「能登柿之助 バターの乱」。
これら一見バラバラに見える食の体験や発見には、一つの共通する精神が流れている。それは、古きを尊び、その価値を深く理解した上で、新しい発想や技術を大胆に掛け合わせ、現代に生きる我々を魅了する新しい価値を創造する「温故知新」の精神だ。
ふと、ある言葉を思い出した。「敗北」という言葉は、「北に負ける」と書く。この言葉の真の意味は、北国の厳しい冬の環境に耐え、春を待つ人々、つまりは、厳しい環境の中で知恵を絞り、努力を重ねた人には敵わない、ということなのだと聞いたことがある。
金沢、そして能登。この北陸の地で生まれた革新的な食文化に触れ、私はその言葉の意味を肌で感じた気がする。厳しい自然、守り継がれてきた豊かな歴史と文化。そうした土壌の中で育まれた人々の、ものづくりに対する真摯な姿勢と、常識に囚われない斬新な発想力には、ただただ敬服するばかりだ。
この素晴らしい挑戦と創造の物語を前に、わが地元、南にあたる九州も負けてはいられない。旅は、まだ見ぬ土地の魅力を教えてくれると同時に、自らの足元を見つめ直し、その価値を再発見するきっかけを与えてくれる。金沢の食が教えてくれた感動と刺激を胸に、私もまた、自分の地元が持つ魅力の探求を続けていきたい。そんな熱い思いを抱かせてくれた、実り多き旅であった。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役