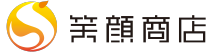先日、ある経営者のプレゼンテーション指導をする機会に恵まれました。彼は聡明で、事業に対する情熱も人一倍。しかし、彼にはプレゼンにおいて、私が「魂の癖」と呼んでいる、根深い弱点がありました。それは、自信のなさからくる早口と、それに伴う情報の詰め込みすぎです。伝えたいことが多すぎるあまり、聞き手の理解が追いつく前に一方的に話を進めてしまい、結果として最も重要なメッセージが霞んでしまう。そんな傾向がありました。
指導にあたり、私はその「魂の癖」を深く理解していました。だからこそ、練習の段階では、その一点に細心の注意を払いました。話すスピード、間の取り方、そして何よりも「何を伝えないか」を決める勇気。私たちは何度も反復練習を重ね、録画とフィードバックを繰り返しました。すると、驚くほど彼は改善されていきました。練習の最終段階では、彼の口から語られる言葉は自信に満ち、聞き手の心を掴む力強さと、心地よいリズムを兼ね備えていました。私は胸をなでおろし、「これなら大丈夫だろう」と、太鼓判を押して彼を本番へと送り出したのです。
しかし、数日後。本番の録音データを送ってもらい、再生ボタンを押した私は、自身の耳を疑いました。そこにいたのは、練習で自信に満ち溢れていた彼の姿ではありませんでした。かつての「魂の癖」が完全に再発していたのです。早口で、情報を詰め込み、聞き手を置き去りにしてしまう、あの頃の彼に逆戻りしていました。
愕然としました。そして同時に、深い問いが頭をもたげました。
なぜ、こんなことが起こるのか?あれほど練習を重ね、完璧にできていたはずのことが、なぜ本番では跡形もなく消え去ってしまったのか?
この問いへの答えは、残酷なほどにシンプルでした。それは、「単なる、練習不足」。この一言に尽きるのです。
「もう十分だ」という幻想
「練習不足だなんて、そんなことはない。あれだけやったじゃないか」
そう反論したくなる気持ちは痛いほどわかります。彼も、そして私も、客観的に見て相当な時間を練習に費やしました。しかし、ここで私たちは「練習」というものの本質を、根本的に捉え直さなければなりません。
練習とは、一体何のために行うのでしょうか?それは、「本番で、最高のパフォーマンスを発揮するため」。ただそれだけです。練習で100回成功しようが、1000回完璧にできようが、たった一度の本番でその力が発揮できなければ、その練習は「不足していた」と言わざるを得ないのです。
スポーツの世界に目を向けてみれば、この事実はより鮮明になります。例えば、世界的な大舞台で活躍するアスリートたち。彼らは、私たち凡人の想像を絶するほどの練習量をこなします。なぜでしょうか?彼らは、本番の舞台が、練習とは全く異なる「魔物」が棲む場所であることを、骨の髄まで理解しているからです。
彼らは知っているのです。練習で「もう十分だ」と感じるレベルは、あくまでスタートラインに過ぎないことを。その「十分」を遥かに超え、身体が、そして魂が、その動きを完全に記憶し、どんな状況下でも自動的に再現できるレベルにまで達しなければ、本番のプレッシャーには到底太刀打ちできないということを。
超一流と呼ばれる人ほど、がむしゃらに、そして謙虚に練習を繰り返します。それは、彼らが自身の才能に驕ることなく、「本番で力を発揮することの難しさ」を誰よりも深く知っているからに他なりません。
本番を支配する「環境」という名の魔物
では、なぜ本番はそれほどまでに難しいのでしょうか。その最大の要因は、**「環境の激変」**です。
いつもの会議室、気心の知れた同僚の前で行う練習。そこは、あなたにとって完璧な「ホーム」です。リラックスでき、心理的な安全性も確保されています。しかし、本番の舞台はどうでしょうか。
強い照明、突き刺さるような何百もの視線、しんと静まり返った巨大なホール、反響する自分の声、予期せぬ機材トラブル…。それらはすべて、練習時には存在しなかった要素です。特に、自分を評価しようと待ち構えている人々、あるいは全く無関心な人々の前で話すという状況は、強烈な「アウェイ」の空間です。
この環境の圧倒的な違いは、私たちの心と身体に想像以上の影響を及ぼします。意識は目の前の聴衆や会場の雰囲気に奪われ、思考は「うまくやらなければ」というプレッシャーで固まります。緊張で心臓は高鳴り、呼吸は浅くなり、手は震え、頭は真っ白になる。こうなってしまえば、練習で培ったはずの繊細な技術や、練り上げた話の構成など、あっという間に吹き飛んでしまいます。練習時の力が100だとすれば、50も出せれば良い方でしょう。多くの人は、20や30しか発揮できずに、悔しい思いを抱えて舞台を降りることになるのです。
もちろん、本番の環境が常に悪いものとは限りません。自分のプレゼンを心から楽しみにしてくれている、温かい拍手で迎えてくれる、そんな応援してくれる人々に囲まれた「ホーム」のような環境も存在するでしょう。そうした時には、アドレナリンが駆け巡り、練習時以上の、120%の力が発揮できることもあります。いわゆる「ゾーンに入る」という状態です。
しかし、人生やビジネスの重要な局面が、常にそんな恵まれた環境である保証はどこにもありません。むしろ、逆境やアウェイの状況でこそ、真価が問われることの方が多いのではないでしょうか。
良い環境もあれば、悪い環境もある。成功もあれば、失敗もある。それが世界のバランスです。そして、「本当に力を発揮する」とは、そのどちらの環境にも備え、どんな状況下でも安定して自分のパフォーマンスを再現できる能力を指すのです。
そのためには、一体何が必要なのでしょうか。
「意識」の限界と「無意識」の領域
その答えの鍵は、**「無意識レベルへの落とし込み」**にあります。
「ええと、次は何を話すんだっけ」「ここで、あのジェスチャーを入れよう」「もう少しゆっくり話すことを意識しないと…」
このように、一つ一つの動作を「意識」しなければ実行できないレベルでは、本番のプレッシャーに耐えることは極めて困難です。なぜなら、先述の通り、本番ではあなたの「意識」というリソースの大部分が、環境の変化への対応や、緊張・焦りといったネガティブな感情の処理に奪われてしまうからです。練習してきたことを思い出し、実行するための「意識」の容量が、ほとんど残されていないのです。
相手の厳しい視線や、会場の重圧に「飲み込まれて」しまえば、意識的にコントロールしようとしていたことは全て崩壊します。そして、最後に残るのは、あなたが最も慣れ親しんだ、元の「癖」だけ。私の指導した社長が、練習の成果を失い、元の「魂の癖」に逆戻りしてしまったのは、まさにこのメカニズムによるものです。彼の改善は、まだ「意識」のレベルに留まっており、「無意識」の領域にまで達していなかったのです。
特に、彼が抱えていたような、生まれ持った気質や長年の習慣に根差した「魂の癖」を根本から変えようとするならば、この「無意識への落とし込み」は絶対に避けて通れない、極めて重要なプロセスとなります。
では、どうすれば、私たちはスキルや知識を「無意識」の領域にまで深く沈めることができるのでしょうか。
無意識への道筋――竈門炭十郎が示した「透き通る世界」
この問いを考えていた時、私の脳裏にふと、ある物語の情景が浮かびました。それは、大人気漫画『鬼滅の刃』に登場する、主人公・炭治郎の父、竈門炭十郎(かまど たんじゅうろう)が語った、神に捧げる「ヒノカミ神楽」の舞の極意です。
病弱でありながら、極寒の中で夜明けまで神楽を舞い続けることができた炭十郎。彼の言葉の中に、意識的な練習が無意識の領域へと昇華していくプロセスが、見事に描き出されています。これは、プレゼンテーションに限らず、あらゆるスキル習得における普遍的な真理を示していると私は感じています。
炭十郎の教えを、スキル習得の段階として紐解いてみましょう。
第一段階:意識的な反復(型を覚えるフェーズ)
炭十郎は、神楽を舞う正しい動きを体に覚えさせることの重要性を説きます。初めのうちは、指の先一本一本にまで神経を張り巡らせ、一つ一つの型を正確に、愚直に繰り返します。この段階は、とにかくきつく、苦しい。全身は筋肉痛になり、無駄な力みも多いため、すぐに疲れてしまいます。
これは、プレゼンの練習でいえば、原稿を丸暗記しようとしたり、不慣れなジェスチャーを意識的に繰り返したりしている段階です。ぎこちなく、不自然で、話している本人も聞いている方も疲れてしまう。しかし、この地道な「型のインプット」なくして、次はありません。全ての土台となる、最も重要なフェーズです。
第二段階:無駄の削ぎ落とし(洗練のフェーズ)
正しい型を何度も何度も繰り返すうちに、体はその動きを記憶していきます。すると、面白いことに、徐々に無駄な力が抜け、動きが洗練されていきます。どこに力を入れ、どこで力を抜けばよいのかを、身体が理解し始めるのです。動きはより自然で、流れるように美しく、そして効率的になっていきます。
プレゼンで言えば、丸暗記した言葉が、次第に自分の言葉として血肉化していく段階です。どこで間を取れば効果的か、どこを強調すれば心に響くか、といったことが感覚的にわかってきます。不自然だったジェスチャーも、言葉と感情に連動した自然な身体表現へと変わっていきます。
第三段階:呼吸法と身体操作(安定と持続のフェーズ)
炭十郎が特に重要視するのが、「息の整え方」、つまり正しい呼吸法です。正しい呼吸を身につけることで、心拍数は安定し、身体の軸もブレなくなる。それによって、疲労を最小限に抑え、長時間にわたって高いパフォーマンスを維持し続けることが可能になります。最小限の動きで、最大限の力を引き出すことができるようになるのです。
これは、プレゼンにおける「呼吸」の重要性と全く同じです。多くの人は緊張すると呼吸が浅くなり、声が上ずり、早口になります。しかし、腹式呼吸を意識し、深く、ゆったりとした呼吸を保つことで、心は落ち着き、声には張りと説得力が生まれます。安定した呼吸は、どんな環境でも自分を見失わないための、強力なアンカーとなるのです。
第四段階:「透き通る世界」(無意識の境地)
そして、これらのプロセスを経て、動きが極限まで洗練された先に待っているのが、炭十郎が語る**「透き通る世界」**です。
これは、もはや何も考えていない、何も意識していない状態。頭の中は雑念なく澄み渡り、まるで自分と周囲の世界の境界線がなくなったかのような感覚。身体は、思考を介さずに、自動的に、そして最も合理的に、完璧な動きを再現します。
この領域に達した時、スキルは完全に「無意識」に落とし込まれたと言えるでしょう。
目の前の聴衆が何人いようと、どんな厳しい視線を向けられようと、予期せぬトラブルが起ころうと、もはや心は揺らぎません。なぜなら、プレゼンを行うという行為が、呼吸をするのと同じくらい、自然で当たり前のことになっているからです。
緊張や焦りといった感情が生まれることすらなく、ただ、そこに在るべき姿として、最高のパフォーマンスが自然に現出する。これが、本当の意味での「習得」であり、凡人と超一流を分かつ決定的な違いなのです。
結論:あなたの「透き通る世界」を目指して
私が指導した社長の失敗は、彼がこの第四段階、すなわち「透き通る世界」に到達する前に、練習を終えてしまったことに起因します。彼のスキルはまだ、意識すればできる「第二段階」や「第三段階」に留まっていました。だからこそ、本番という非日常の環境に「意識」を奪われた瞬間、すべてが崩れ去り、根深い「魂の癖」が顔を出してしまったのです。
この経験は、私自身にとっても大きな教訓となりました。何かを教える、伝えるということは、単に技術や知識を右から左へ受け渡すことではありません。相手がそれを無意識の領域にまで落とし込み、どんな逆境でも再現できる「本物の力」に変えるまで、寄り添い、導くことなのだと。
そして、これはプレゼンテーションに限った話ではありません。あなたが今、習得しようとしているスキル、克服しようとしている弱点、達成しようとしている目標、そのすべてに共通して言えることです。
「練習でできるようになったから、もう十分だ」
そう感じた時こそ、本当の練習の始まりなのかもしれません。それはまだ、意識の海を泳いでいるに過ぎないのですから。目指すべきは、その遥か先、深く静かな無意識の海底です。
そこに至る道は、竈門炭十郎が示したように、地道で、苦しく、果てしなく感じられるかもしれません。しかし、その苦しみを乗り越え、無駄を削ぎ落とし、呼吸を整え、反復を続けた者だけが見ることのできる「透き通る世界」が、確かに存在します。
その境地に立った時、あなたは初めて、環境やプレッシャーといった外部の要因から完全に解放され、いつでも、どこでも、ありのままの自分、最高の自分を発揮できる、真の自由を手に入れることができるのです。
あなたの「ヒノカミ神楽」は何ですか? あなたが目指すべき「透き通る世界」は、どこにありますか? その答えを見つける旅は、今、この瞬間から始まっています。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役