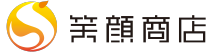「お寿司も、しゃぶしゃぶも、天ぷらも、全部食べ放題!」
そんな夢のような謳い文句を掲げる全国チェーンの飲食店。美食家を自称する友人に誘われ、先日その店に足を運んでみました。グルメサイトの口コミも上々で、週末は予約必須の人気店のようです。
店内に入ると、活気に満ち溢れた声と美味しそうな出汁の香りが迎えてくれます。価格設定は実に戦略的。最もリーズナブルなコースは2,000円台、 スタンダード(真ん中)が3,000円台、そして豪華なプレミアムコースが4,000円台と、予算に応じて選べる3段階の料金体系です。私たちは、品数と価格のバランスが良さそうな3,000円台の真ん中のコースを選択。制限時間は90分一本勝負です。
次々と運ばれてくる料理の数々。正直に言えば、一貫数百円もするような高級寿司店や、老舗の天ぷら屋さんの味には及びません。しかし、それを補って余りあるほどの圧倒的な品揃えと、この価格を考えれば十分に満足できるクオリティです。「コスパが高い」とは、まさにこのことでしょう。
しかし、食べ放題の喧騒の中でふと冷静になったとき、一つの巨大な疑問が頭をもたげました。
「なぜ、これほどまでに安く提供できるのだろうか?」
その答えを探求していくうちに、私は現代の外食産業が抱える、光と影、そして誰もが目を背けたくなるような「不都合な真実」に突き当たることになったのです。
安さの秘密 ①:徹底的に効率化された「未来のレストラン」
この店の驚異的なコストパフォーマンスの裏側には、血の滲むような企業努力と、テクノロジーを駆使した徹底的なオペレーションの効率化がありました。
セントラルキッチンという心臓部
まず考えられるのが、セントラルキッチンシステムの導入です。これは、全国の店舗で提供する食材のカットや下味付けといった下ごしらえを、一か所の集中調理施設でまとめて行う方式です。各店舗に配送された食材は、店内で揚げるだけ、煮るだけといった最小限の調理で済むようになっています。
これにより、店舗ごとの調理人の技術レベルに味が左右されることなく、全国どこでも均一な品質の料理を提供できます。さらに、店舗での調理工程が簡略化されるため、専門的な技術を持つ高給な料理人を多数配置する必要がなくなります。これが、人件費を大幅に削減できる第一のカラクリです。
ホールを支配するテクノロジー:タッチパネルと配膳ロボット
席に着いて驚いたのは、店員さんを呼ぶ声がほとんど聞こえないことでした。それもそのはず、注文はすべてテーブルに設置されたタッチパネルで行います。顧客が画面をタップすると、注文データは瞬時に厨房のモニターに送信されます。これにより、オーダーミスの削減と、注文を受けるためだけにホールスタッフがテーブル間を奔走する必要がなくなります。
そして、この店の効率化を象徴するのが、店内を縦横無尽に走り回る配膳ロボットの存在です。
厨房で出来上がった料理は、このロボットのトレーに乗せられます。ロボットは、タッチパネルからの注文データに基づき、指定されたテーブルまで最短ルートを自律走行し、料理を届けてくれるのです。
この配膳ロボットの導入効果は絶大です。
・人手不足の解消:少子高齢化が進む日本において、飲食業界の人手不足は深刻な経営課題です。ロボットが配膳という重労働を肩代わりすることで、少ないスタッフでも店舗運営が可能になります。
・スタッフの負担軽減:大量の皿や重い鍋を運ぶ作業は、スタッフの身体に大きな負担をかけます。ある大手ファミリーレストランの事例では、配膳ロボット導入後、フロアスタッフの1日の歩行数が42%も減少したというデータもあります。これにより、スタッフの疲労が軽減され、離職率の低下にも繋がります。
・接客品質の向上:スタッフは配膳業務から解放された時間と労力を、おもてなしや顧客とのコミュニケーションといった、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中させることができます。
・労働力の多様化:高度な日本語能力や接客スキルが求められないため、外国人労働者でも即戦力として活躍しやすくなります。
この「タッチパネル注文+配膳ロボット」という組み合わせは、人件費を極限まで圧縮するための最強のタッグと言えるでしょう。
規模の経済という最終兵器
そして忘れてはならないのが、全国に店舗を展開するチェーン店だからこそ享受できる「規模の経済(スケールメリット)」です。食材を一度に大量に仕入れることで仕入れコストを大幅に下げ、セントラルキッチンや物流システムへの大規模な投資も、店舗数で割れば一店舗あたりの負担は小さくなります。
これらの要因が複雑に絡み合い、3,000円台という価格での「寿司・しゃぶしゃぶ・天ぷら食べ放題」が実現されているのです。その巧みな経営戦略には、正直、感嘆せざるを得ませんでした。しかし、その感動は、テーブルに置かれた一滴の「醤油」によって、もろくも崩れ去ることになるのです。
安さの秘密 ②:醤油が語る、見えないコストの正体
ふと、テーブルに置かれた醤油さしに目をやると、「こいくち醤油(本醸造)」と書かれたラベルが貼られていました。「本醸造」と聞くと、伝統的な製法で作られた本格的な醤油というイメージがあります。しかし、職業柄、食品の原材料表示を確認する癖がついている私は、その裏に書かれた小さな文字に目を疑いました。
【原材料名】脱脂加工大豆、小麦、食塩、果糖ぶどう糖液糖、大豆/アルコール
この文字列を見た瞬間、私の背筋に冷たいものが走りました。そして、この店に二度と来ることはないだろうと、心に固く誓ったのです。
もちろん、この店だけを責めるつもりはありません。これは、現代の多くの外食産業、加工食品業界が抱える根深い問題の氷山の一角に過ぎないのです。
多くの飲食店の店主は、「お客様に美味しいものをお腹いっぱい食べてほしい」という純粋な想いで店を経営しているはずです。彼らに悪気はないでしょう。問題なのは、彼ら自身も、自分が使っている食材の正体をよく知らないまま、コストや利便性を優先する納入業者の言うことを鵜呑みにしてしまっているケースが少なくないのではないか、ということです。(そして、その業者自身も、深い知識を持っていないのかもしれません。)
「日本は安全な国だ」「同じ日本人が、体に悪いものを売るはずがない」
私たちは、本来自分たちで学び、判断しなければならないことを怠り、何の根拠もない「信頼」に身を委ねてしまってはいないでしょうか。皮肉なことに、その思い込みこそが、私たちの、そして特に未来を担う子どもたちの食の安全を静かに脅かしているのかもしれないのです。
価格や見た目の華やかさに惹かれて流行る店の裏側で、一体何が起きているのか。今回は、あの醤油の原材料名にあった2つのキーワード、「脱脂加工大豆」と「果糖ぶどう糖液糖」の正体に迫ってみたいと思います。
原材料 ①:「脱脂加工大豆」とは何か?
「脱脂加工大豆」と聞いても、多くの人はピンとこないかもしれません。これは、油を搾り取った後の大豆カスのことです。
製造工程の裏側
本来、伝統的な醤油は「丸大豆」を原料とします。しかし、現在、日本で生産される醤油の約8割は、この脱脂加工大豆から作られています。なぜなら、大豆から大豆油を製造する過程で、大量の「搾りカス(脱脂加工大豆)」が副産物として生まれるからです。
その製造工程では、「ヘキサン」という化学溶剤が使われます。ヘキサンは、ガソリンにも含まれる石油系の有機溶剤で、大豆をこの液体に浸すことで効率的に油分を抽出します。もちろん、製造工程の最後にヘキサンは蒸発させて除去するため、最終製品には残留しないよう厳格に管理されている、とされています。しかし、化学溶剤を使って加工された食品を、私たちは本当に「自然」なものと呼べるのでしょうか。
失われる風味と、生まれる「キレ」
脱脂加工大豆を使うことで、醤油本来の風味は確実に失われます。
・油脂由来の香り: 油に溶けやすい豊かな香気成分が、油を搾る工程で一緒に取り除かれてしまいます。
・まろやかさとコク: 丸大豆の油分は、発酵の過程でグリセリンなどの成分に分解され、醤油に上品な甘みとまろやかなコクを与えます。この工程が大幅に失われます。
では、なぜ脱脂加工大豆で作った醤油にも風味があるのでしょうか。それは、発酵の過程で麹菌や酵母が、タンパク質を分解してアミノ酸(うま味成分)を、糖を分解して300種類以上もの香気成分を新たに生み出すからです。
むしろ、油分がない分タンパク質の濃度が高いため、より多くのアミノ酸が生成され、「キレのある強いうま味」が生まれます。しかし、それは丸大豆醤油が持つ、奥深く、まろやかな風味とは全くの別物です。失われた「まろやかさ」や「コク」を補うために、後述する別の添加物が使われることも少なくありません。
原材料 ②:「果糖ぶどう糖液糖」という甘いワナ
醤油の原材料として、もう一つ看過できないのが「果糖ぶどう糖液糖」です。これは「異性化糖」とも呼ばれる液状の甘味料で、トウモロコシやジャガイモのデンプンを原料に、酵素を使って人工的に作り出されたものです。
なぜ醤油に「甘味料」が必要なのか?
醤油に甘味料が使われる最大の理由は、九州地方などで好まれる「甘口醤油」の文化に対応するためです。しかし、それだけではありません。
・コスト削減:砂糖よりもはるかに安価に製造できます。
・加工の容易さ:液体なので混ざりやすく、溶かす手間もかかりません。
・風味の調整:前述の脱脂加工大豆を使った醤油に不足しがちな「コク」や「まろやかさ」を、この甘味料で補うという側面もあります。
しかし、この果糖ぶどう糖液糖には、その安さと便利さの代償として、深刻な健康リスクが潜んでいることが、近年の研究で次々と明らかになっています。
安全性への重大な懸念
[1] 原料のほとんどが「遺伝子組み換え」 果糖ぶどう糖液糖の原料となるトウモロコシの約9割以上が、遺伝子組み換え(GM)作物であると言われています。日本では、製造過程で遺伝子やタンパク質が分解・除去されるため、最終製品に表示する義務がありません。私たちは、知らないうちに大量の遺伝子組み換え食品を口にしている可能性があるのです。
[2] 老化を促進する物質「AGEs」の大量発生 最大の問題は、果糖が体内で糖化(タンパク質と結びつくこと)する際に発生する「AGEs(終末糖化産物)」という老化促進物質です。果糖は、なんとブドウ糖の8〜10倍ものAGEsを生成することが分かっています。このAGEsは、一度体内で作られると分解されにくく、血管、脳、皮膚など全身に蓄積して老化を早め、がんや糖尿病、動脈硬化、認知症などのリスクを高めることが指摘されています。
[3] 肥満・糖尿病への直結ルート 果糖は、ブドウ糖と代謝経路が異なり、そのほとんどが肝臓で直接代謝され、中性脂肪に変換されやすい性質を持っています。これが、非アルコール性脂肪肝や肥満、糖尿病の大きな原因となります。血糖値を直接的には上げにくいため「ヘルシー」という誤解が広まった時期もありましたが、今ではその危険性が広く認識されています。
世界の規制と日本の現状
食の安全に対する意識が高いヨーロッパ(EU)では、乳児用粉ミルクへの使用が禁止されるなど、異性化糖の使用に厳しい規制がかけられています。アメリカでも、その使用を見直す動きが広がっており、大手飲料メーカーが「本物の砂糖」への回帰を模索し始めています。
残念ながら、日本の規制は世界に比べて緩やかです。私たちは、自らの知識で自衛するしかないのが現状なのです。
私たち消費者にできること:希望の光はどこに?
効率化とコストカットを極限まで追求した結果、安くて便利な食が手に入るようになった現代。しかしその裏側で、私たちは本来の「食」が持つ豊かさや安全性を少しずつ失っているのかもしれません。
そんなことを考えていた矢先、私は偶然、一軒の老舗中華料理店を見つけました。おそらく日本に帰化した中国人のご家族が経営されている、地域に根差した小さなお店です。メディアで取り上げられることもある有名店のようですが、価格は驚くほどリーズナブル。厨房では多くの中国人料理人たちが、そしてホールでは配膳スタッフが、まるで人海戦術のように活気よく働いています。
その店の壁に、一枚の張り紙がありました。
「当店は化学調味料、添加物は一切使用しておりません。当店で使用している醤油も全て手作りです。」
その文字を見たとき、私は胸が熱くなるのを感じました。
かたや、配膳ロボットとセントラルキッチンで効率化を極め、添加物で整えられた味を安価に大量供給する巨大チェーン店。 かたや、多くの人の手を使い、手間暇を惜しまず、伝統的な製法で本物の味を守り続ける小さな老舗。
これから先、一体どちらの店が生き残っていくのでしょうか。いや、どちらの店を私たちは「選ぶ」べきなのでしょうか。
先日、ある元マスコミ関係者の方が「情報は『従う』ものから『判断』するものへと変わった」と話されていました。まさに今の時代を言い当てた言葉だと思います。
安さには、必ず理由があります。食品の裏側に書かれた小さな原材料表示は、その理由を解き明かし、私たち自身が「判断」を下すための重要な情報です。
その情報を知り、自らの知識と価値観で吟味し、私たちは何を選び、何を食べ、どう生きていくのか。便利で豊かなこの時代だからこそ、一人ひとりの情報への、そして「食」への向き合い方が、今、問われているのです。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役