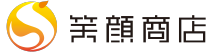はじまりは、ホテルの片隅にあった一枚の案内図
旅先での食事は、いつだって心を躍らせるものだ。特に予定を決めず、その場の空気と直感に任せて店を選ぶ時間は、旅の醍醐味の一つと言えるだろう。東京出張の夜、日本橋のホテルで少し手持ち無沙汰にしていた私は、部屋のデスクに置かれていた一枚の観光案内に目をやった。そこには、老舗の風格を漂わせる一軒の寿司屋の写真と名前が記されていた。「吉野鮨本店」。その名に、なぜか強く心が惹かれた。歴史の重みを感じさせるその佇まいに、何か特別な物語が隠されているような気がしたのだ。
「よし、行ってみよう」。衝動的な決断だった。地図を頼りにホテルを出て、日本橋のオフィス街を歩くこと約15分。近代的なビル群の間に、そこだけ時が止まったかのような趣のある店構えが見えてきた。
土曜日の昼12時前。店の前には既に長い行列ができていた。ビジネスマン、観光客、地元の常連と思しき人々。その誰もが、これから味わう一貫に期待を寄せているのが見て取れた。人気店の証である行列に少し気圧されながらも、最後尾につける。待つこと、およそ20分。ようやく「どうぞ」と声がかかり、歴史が刻まれた暖簾をくぐった。
江戸の粋と心意気。カウンターで味わう本物の鮨
店内は、想像していたよりもずっと広く、活気に満ちていた。手入れの行き届いた白木のカウンター、奥にはテーブル席、そして二階席もあるようだ。案内されたカウンター席に腰を下ろすと、目の前では四人の板前が、無駄のない流れるような動きで次々と鮨を握っている。その真剣な眼差しとリズミカルな手さばきは、もはや職人芸の域に達しており、見ているだけで心が満たされていくようだった。
「東京の、しかも日本橋の寿司屋だから、さぞかしお高いのだろうな」。正直、懐具合を気にしながらメニューを開いた。しかし、そこに記されていた価格は、良い意味で私の予想を裏切るものだった。おまかせにぎりは7貫、9貫、11貫とあり、最も多い11貫でも4,400円(税込)。もちろん、一貫単位での追加も可能だ。昨今、都心の寿司屋ではコースで数万円という店も珍しくない中、この価格設定は驚きであり、老舗の懐の深さを感じさせた。
迷わず11貫のおまかせを注文する。ほどなくして、目の前のつけ台に一貫、また一貫と、美しい鮨が置かれていく。少し硬めに締められたシャリは、口の中でほろりと解け、ネタの旨味を最大限に引き立てる。旬の魚介を中心としたネタは、どれも新鮮そのもの。丁寧な仕事が施された光り物、とろけるような食感の白身、濃厚な旨味の赤身。一貫ごとに、江戸前寿司の奥深さを改めて教えられるようだった。
寿司、天ぷら、そば。江戸のソウルフードが辿った道
美味しい鮨を頬張りながら、ふと、江戸時代の食文化に思いを馳せていた。鮨、天ぷら、そば。これらは元々、屋台で気軽に楽しむ、江戸の庶民のソウルフードだったはずだ。そして、ここ日本橋や神田は、まさしくその江戸の中心地であり、神田明神がその営みを見守ってきた場所である。
本来、江戸の大衆的な食の代表格であったはずの鮨が、いつからこれほどまでに高級な食べ物になってしまったのだろうか。以前、懇意にしている蕎麦屋の亭主が嘆いていた言葉を思い出した。「昔はさ、鮨も天ぷらもそばも、みんな同じような大衆価格だったんだよ。それが今じゃ、鮨だけが飛び抜けちまって、俺たちとは違う世界の食べもんになっちまった」。
彼の言葉は、現代の食文化の一面を的確に捉えている。もちろん、高級店が提供する唯一無二の体験には価値がある。しかし、誰もが気軽に「今日は寿司でも食いに行くか」と言えなくなった現状には、一抹の寂しさを感じずにはいられない。
だが、この「吉野鮨本店」は違う。明治12年創業という、他に類を見ないほどの歴史と格式を持ちながらも、頑なに大衆が手の届く価格帯を守り抜いている。これこそが、この店が140年以上にわたって愛され続ける理由なのだろう。伝統や味を守るだけでなく、その文化を享受する人々の懐までをも守る。その心意気に、私は深く感動した。「あっぱれな老舗だ」。心の底からそう思った。この一軒の店を見る限り、日本はまだ捨てたものではない。そんな希望さえ湧いてくるのだった。
鮨はなぜ高くなったのか?日本の海の悲鳴
感動的な食体験を終え、店を後にした私の頭には、新たな疑問が浮上していた。「そもそも、なぜ寿司はこんなにも高くなってしまったのだろうか」。その答えの一端は、日本の海が抱える深刻な問題にあるのかもしれない。近年の日本の水産物の漁獲量が、危機的なレベルで減少し続けているという事実だ。
日本の魚を獲る技術は、間違いなく世界一だろう。魚群探知機の性能、網の技術、鮮度を保つための知恵。どれをとっても他国の追随を許さないレベルにある。それにもかかわらず、日本の漁獲高は下がり続け、世界的に見れば「一人負け」の状態なのである。国際連合食糧農業機関(FAO)の統計を見ても、世界の漁獲・養殖生産量が右肩上がりに伸びているのに対し、日本の漁獲量は1984年の1,282万トンをピークに減少し続け、2022年には392万トンと、ピーク時の3分の1以下にまで落ち込んでいる。
サンマやスルメイカ、サケといった食卓でお馴染みの魚の不漁は、毎年のようにニュースで報じられる。このままでは、美味しい寿司が食べられなくなるどころか、日本の豊かな魚食文化そのものが失われてしまうのではないか。
その原因は、決して一つではない。地球温暖化による海水温の上昇は、魚の生息域を変え、生態系に深刻な影響を与えている。漁業従事者の高齢化と後継者不足も深刻だ。2024年の統計では、漁業従事者のうち65歳以上が約4割を占め、若者のなり手は減る一方だという。さらに、原油価格の高騰による燃料費の上昇は、漁師たちの経営を直接圧迫している。
そして、これらの問題と並んで、いや、それ以上に根深い問題として指摘されているのが、「資源管理の失敗」、特に「稚魚の乱獲」である。
未来の魚を食い潰す「成長乱獲」という罪
「成長乱獲」。それは、本来であればもっと大きく成長し、何度も産卵して子孫を残してくれるはずの小さな魚(稚魚・未成魚)を、根こそぎ獲ってしまう行為を指す。大きくしてから獲る方が、総重量も増え、経済的にも効率が良いはずなのに、目先の利益のために小さな魚まで獲り尽くしてしまうのだ。
水産庁の資料によれば、例えばマアジの漁獲のほとんどが、産卵前の0歳魚と1歳魚で占められているという。これは衝撃的な事実だ。次世代を担うべき親魚が、その役目を果たす前に市場に出荷されてしまっているのだ。かつて豊かな資源を誇ったハタハタが枯渇状態に陥ったのも、稚魚の乱獲が大きな原因であったと言われている。
驚くべきことに、こうした「成長乱獲」は、世界的に見れば非常に特殊な状況だ。例えば、漁業大国であるノルウェーでは、魚種ごとに厳格な最小漁獲サイズが定められており、それより小さな魚を獲ることは法律で禁じられている。科学的データに基づいた資源管理が徹底され、持続可能な漁業が実現されているのだ。
なぜ日本では、このような野放図な状態が続いているのか。そこには、制度的な不備はもちろんのこと、私たちの意識の根底にある、より深刻な問題が横たわっているように思えてならない。「自分だけが変わっても何も変わらない」「俺が獲らなくても、どうせ他の誰かが獲る」。そんな無責任な発想が、日本の豊かな海を蝕んでいるのではないだろうか。
そして、この「自分さえよければいい」という個人主義的な思考は、どこから来たのだろう。戦後、GHQの指導のもとで行われた教育は、日本の伝統的な共同体意識や道徳観を解体し、個人を優先する価値観を植え付けた、という見方がある。もちろん、全ての原因をそこに帰結させるのは短絡的かもしれない。しかし、国や共同体といった大きな視点よりも、まず個人の利益を優先する風潮が、資源の枯渇という形で社会に跳ね返ってきているのだとしたら、私たちは今こそ、その意識を一人ひとりが変えていかなければならない。このままでは、本当に日本の未来はない。
「吉野鮨本店」の暖簾が守るもの
日本橋の雑踏を歩きながら、私の思考は、一軒の寿司屋から日本の漁業、そして国民の意識の問題へと大きく飛躍していた。暗澹たる気持ちになりかけたその時、先ほどまでの感動が鮮やかに蘇ってきた。
ー そうだ、「吉野鮨本店」があるじゃないか。
あの店は、ただ美味しい鮨を安く提供しているだけではない。トロ握り発祥の店として、鮪のそれまで捨てられていた部位に価値を見出し、新たな食文化を創造した。毎朝河岸で最高の魚を仕入れ、粕酢と塩だけで作る伝統のシャリを守り続ける。その実直な仕事の積み重ねが、140年以上の歴史を紡いできたのだ。
「吉野鮨本店」の暖簾が守っているのは、伝統の味だけではない。それは、江戸から続く食文化への敬意であり、資源への感謝であり、そして、庶民のささやかな楽しみを未来へと繋いでいこうとする、揺るぎない心意気そのものではないだろうか。彼らのように、目先の利益にとらわれず、長い目で物事を捉え、自らの仕事に誇りを持つ。そんな姿勢こそが、今の日本に最も必要なのかもしれない。
一軒の老舗寿司屋での偶然の出会いが、日本の食と海の未来について、深く考えるきっかけを与えてくれた。私たちが、この先もずっと美味しい魚を食べ続けられるかどうかは、資源管理という大きな枠組みの改革と同時に、生産者から消費者まで、海に関わる全ての人の意識変革にかかっている。
今度、寿司屋のカウンターに座ることがあったら、目の前の一貫に込められた職人の技と、その向こうに広がる日本の海の物語に、少しだけ思いを馳せてみてほしい。その小さな想像力こそが、未来を変える第一歩になるはずだから。
店舗情報:吉野鮨本店
・歴史:明治12年(1879年)創業。「トロ握り」発祥の店として知られる、140年以上の歴史を誇る日本橋の老舗。
・住所:〒 103-0027 東京都中央区日本橋3-8-11
・アクセス:地下鉄「日本橋駅」より徒歩1分 / JR「東京駅」より徒歩10分
・営業時間:< 月 ~ 金 > 11:00〜14:00 / 16:30〜21:30 ・ < 土 > 11:00〜14:00
・定休日:日曜日、祝日、金曜日が祝日の場合の土曜日
・特徴:伝統的な製法を守る江戸前鮨を、格式張らない雰囲気の中でリーズナブルに楽しめる。粕酢(赤酢)と塩のみで作る甘味のないシャリが特徴。
・注意点:支払いは現金のみ。特に土曜日のランチタイムは混雑するため、時間に余裕を持って訪れることを推奨。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役