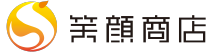旅はいつも、予期せぬ出会いに満ちている。計画通りに進む安心感も良いが、ふとした偶然が、その後の人生に思いがけない彩りを加えてくれることがある。先日訪れた金沢での体験は、まさにそんな「出会い」と呼ぶにふさわしいものだった。
プロローグ:導かれるように出会った店
加賀百万石の城下町、金沢。その歴史の香りが色濃く残る尾山神社周辺を散策していた時のことだ。急ぎの電話をかける必要があり、賑やかな大通りから一本、静かな裏通りへと足を踏み入れた。用事を済ませ、ふと顔を上げると、そこにその店はあった。古美術品や骨董品を扱うような、歴史を感じさせる佇まいの店。しかし、ガラス越しに見えるのは、紛れもない「刀」だった。
最初からその店を知っていたわけではない。完全に偶然だった。いや、今思えば、何かに引き寄せられたのかもしれない。店の名は特に記憶に残っていない。ただ、そこに吸い込まれるように入っていったことだけは鮮明に覚えている。
店内には、歴史の教科書や時代劇で見た名だたる武将たちのレプリカの刀が、静かな威厳を放ちながら並んでいた。最初に僕の目を釘付けにしたのは、前田慶次の刀だった。朱色を基調とした色鮮やかな鞘のデザインは、見る者の心を躍らせる。常識や権威に屈せず、自らの「好き」を貫き通した「かぶきもの」と称された男の生き様が、その一本に凝縮されているかのようだった。
その隣には、軍神と謳われた上杉謙信の刀、そして戦国最後のヒーローとして僕が敬愛してやまない真田幸村の「六文銭」が刻まれた刀も並んでいる。心が沸き立つような感覚だった。ふと、武田信玄の刀に目をやると、店主が優しく声をかけてくれた。
「武田信玄は、基本的に馬の上で戦うことが多かったので、これは刀よりも少し長い『太刀(たち)』なんですよ。馬上で抜きやすいように、刃を下にして腰に佩(は)くんです」
なるほど、一つ一つの道具には、その持ち主の戦い方や生き方までが反映されているのだ。店主の丁寧な説明を聞きながら、僕はすっかりその世界に魅了されていた。
なぜ「家康」を選んだのか
正直に言えば、何かを買うつもりなど毛頭なかった。ただのウィンドウショッピングの延長線上にある、偶然の立ち寄りに過ぎなかったはずだ。しかし、それぞれの刀に込められた物語や、その背景にある武将たちの生き様に触れるうちに、心の奥底から「欲しい」という感情が湧き上がってくるのを感じた。それは、単なる所有欲とは違う、もっと深い、何か精神的な繋がりを求めるような感覚だった。
そして、僕の視線は一本の刀に吸い寄せられた。徳川家康の刀だ。派手さはない。むしろ、質実剛健という言葉がしっくりくる。しかし、その静かな佇まいの中には、天下を統一し、260年以上にわたる泰平の世を築き上げた男の、計り知れない重みと深みが宿っているように感じられた。
いつの間にか僕は、どの刀を買うべきか本気で悩んでいる自分に気づき、少し可笑しくなった。前田慶次の華やかさにも、真田幸村の悲劇的な英雄性にも強く惹かれる。しかし、最終的に僕が手に取ったのは、徳川家康の刀だった。
店主曰く、最近、ジェームズ・クラベルの小説を原作としたドラマ『SHOGUN』の影響で、欧米からの観光客が徳川家康の刀をこぞって買っていくらしい。彼らにとって家康は、日本の歴史を理解する上での重要なアイコンなのだろう。しかし、僕が家康を選んだ理由は、それとは少し違う。その時はまだ漠然としていたが、僕自身の人生の指針となる何かを、この刀の中に見出していたのかもしれない。
シンクロニシティ:家康が僕を呼んでいる?
不思議なことは、その刀を購入してから始まった。まるで、僕の周りで「徳川家康」というキーワードが頻繁に点滅し始めたかのように、関連する情報が次々と舞い込んでくるようになったのだ。これは心理学でいう「カラーバス効果(特定の一つを意識し始めると、それに関する情報が無意識に自分の手元にたくさん集まるように感じる現象)」かもしれない。しかし、それにしてもあまりに偶然が重なりすぎていた。
ある時は、テレビで徳川家康が祀られている日光東照宮の特集が組まれているのをたまたま目にした。またある時は、仕事で東京を訪れた際、何の気なしに立ち寄ったのが、江戸の総鎮守であり家康とも縁の深い神田明神だった。さらにその近くで、徳川家とゆかりのある福徳神社に参拝する機会にも恵まれた。
極めつけは、ある人から聞いた「徳川家ゆかりの菓子」の話だ。その菓子は、添加物を一切使わない伝統的な製法を守っているため、日持ちがしない。賞味期限はわずか2日。現代の流通の観点からすれば、非常に「買いづらい」商品だ。しかし、それでもなお店が続いているのは、その不便さをも凌駕する価値を理解し、選び続ける人々がいるからに他ならない。その話を聞いた時、僕はハッとした。これもまた、家康の哲学に通じるものではないかと。
そして、改めて学んだ事実。徳川幕府は、世界史的に見ても極めて長く続いた政権であるということ。約260年もの間、大きな戦乱のない平和な時代を維持した。この事実に、僕は改めて畏敬の念を抱いた。
金沢で手にした一本の刀。それがきっかけで、僕の日常は徳川家康という存在と共鳴し始めた。考えすぎかもしれない。だが、僕はこう思わずにはいられなかった。「この刀には、徳川家康がついているのかもしれない」と。僕は、この刀を単なる飾り物ではなく、何か特別な意味を持つ存在として、大切にしようと心に決めた。
巨星の哲学に学ぶ:山岡荘八『徳川家康』再訪
この一連の不思議な体験は、僕にかつて夢中で読んだ一冊の長編小説を思い出させた。山岡荘八による不朽の名作、『徳川家康』だ。全26巻、原稿用紙にして17,400枚に及ぶこの壮大な物語を、僕は文字通り寝食を忘れて読みふけった。そして、読み終えた時には、すっかり家康という人物のファンになっていた。
この小説は、単なる歴史物語ではない。それは、組織論であり、リーダーシップ論であり、そして人生哲学の書でもある。かつて中国で最も売れている本の一つに、この山岡荘八の『徳川家康』があったという話を聞いたことがある。国も時代も超えて、人々がこの物語に惹きつけられるのは、そこに普遍的な「帝王学」のエッセンスが詰まっているからだろう。
Wikipediaで改めて調べてみると、この作品の持つ社会的影響力の大きさに驚かされる。
山岡荘八著『徳川家康』
・刊行期間: 1953年 – 1967年(新聞連載は1950年から17年間)
・規模: 全26巻。かつてギネスブックに「世界最長の小説」の一つとして認定された。
・執筆動機: 著者の山岡荘八は、戦争で散っていった若者たちが願った日本の存続と世界平和への思いを、家康が目指した「泰平の世」に重ね合わせて描こうとした。
・社会的影響: 1960年代、多くの経営者がこの本を「社長の虎の巻」として愛読し、一大ブームとなった。忍耐と長期的視野を持つリーダーとしての家康像は、戦後復興期の日本人に深い感銘を与え、それまでの「狸爺」というイメージを刷新した。
多くの経営者やリーダーたちが、この本から組織をまとめ、人を動かし、長期的なビジョンを実現するための知恵を学んだ。僕が金沢で家康の刀に惹かれたのも、この小説を通して知った家康の人間性や哲学が、心のどこかに深く刻み込まれていたからに違いない。
家康の言葉に宿る「未完成」の美学
『徳川家康』を読み、僕の心に深く刻まれた言葉がある。
人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。 不自由を常と思えば不足なし。 勝つことばかり知りて負くるを知らざれば、害その身に至る。 おのれを責めて人を責めるな。 及ばざるは過ぎたるよりまされり。
これは家康の遺訓とされる言葉だが、特に後半の三つは、現代を生きる我々にとって非常に重要な示唆に富んでいる。
「勝つことばかり知って、負けを知らないことは危険である」 「自分の行動について反省し、人の責任を追及してはならない」 「足りないくらいのほうが、やり過ぎてしまっているよりも優れている」
この「及ばざるは過ぎたるよりまされり」という言葉に、僕は家康の哲学の真髄を見る思いがする。
かつて、日本の製造業は、その「完璧主義」を武器に世界を席巻した。寸分の狂いもなく、同じ品質のものを大量に生産する能力は、第二次産業の時代において圧倒的な強みだった。しかし、時代は変わった。イノベーションが絶えず求められる現代において、その完璧主義は時として足かせになる。なぜなら、「完璧」とは、完成した瞬間に崩壊が始まる状態でもあるからだ。それ以上の発展、つまり「伸び代」がない。
ここに、徳川家康の驚くべき知恵がある。日光東照宮の陽明門には、無数の豪華絢爛な彫刻が施されているが、その中の一本の柱だけが、意図的に逆さまに取り付けられている。「魔除けの逆柱」と呼ばれるこの柱は、「建物は完成した瞬間から崩壊が始まる」という考えに基づき、わざと未完成な部分を残すことで、災いを避けるという願いが込められている。
家康は、意図的に「未完成」を作り出し、「伸び代」を残すことの重要性を知っていたのではないか。徳川幕府が260年という世界史上稀に見る長期政権を維持できたのは、武力や権力だけでなく、こうした柔軟で持続可能な思想を持っていたからかもしれない。「完璧」を目指して硬直化するのではなく、常に変化の余地を残しておく。その哲学こそが、泰平の世の礎となったのだ。
現代に生きる徳川の知恵と日本の未来
この「未完成の美学」「伸び代の思想」は、現代のビジネスや社会にも通じる。先ほど触れた徳川家ゆかりの無添加和菓子の話。賞味期限が2日というのは、現代の視点から見れば「不便」で「不完全」かもしれない。しかし、その「足りなさ」が、逆に「本物であること」「安心安全であること」の何よりの証明となっている。そして、それが強力なブランド価値を生み、時代を超えて人々から選ばれ続けている。まさに「及ばざるは過ぎたるよりまされり」の実践例だ。
僕たちが今生きる日本もまた、大きな変革期にあることは間違いない。先日、高市早苗氏が自民党の新総裁に選出された。彼女が公言している政策を実行すれば、日本経済は再び上向くかもしれないという期待がある。しかし、その前には巨大な抵抗勢力が立ちはだかることも事実だ。もし彼女が、この国を覆う閉塞感を打ち破る改革を成し遂げられないのであれば、自民党という組織そのものが「完成し、崩壊が始まる」段階に来ているのかもしれない。
歴史を振り返ると、北条政子しかり、日野富子しかり、思い切った改革や時代の転換点を主導したのは、男性よりもむしろ女性であったケースが少なくない。これは単なる偶然ではないだろう。既存のシステムを完璧に維持しようとする「男性性」に対し、状況に応じて柔軟に変化し、新たな生命を生み育む「女性性」のエネルギーが、硬直化した社会に風穴を開けるのかもしれない。変革の時代には、完璧な完成品ではなく、生命力に満ちた「未完成」な伸び代こそが必要なのだ。
エピローグ:一本の刀から始まった思索の旅
金沢の裏通りで手にした一本のレプリカの刀。それは、僕にとって単なる美しい置物ではなくなった。この刀を眺めるたびに、僕は徳川家康という巨人の哲学に思いを馳せる。
完璧でなくてもいい。むしろ、少し足りないくらいがいい。そこにこそ、成長の余地があり、持続可能性が生まれる。勝ち続けることだけを目指すのではなく、負けから学ぶ謙虚さを持つ。人のせいにせず、まず自らを省みる。
この刀は、時を超えて僕にそう語りかけてくるようだ。金沢での偶然の出会いから始まったこの思索の旅は、僕自身の生き方、そしてこれからの日本のあり方を考える、深く、そして豊かな時間を与えてくれている。
これからも僕は、この刀を傍らに置き、家康の知恵に学びながら、この変化の激しい時代を歩んでいきたい。心からそう思う。この出会いに、感謝を込めて。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役