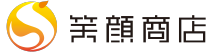先日、長年の念願だった有馬温泉へ、妻と二人で訪れました。九州に住む私たちにとって、関西の奥座敷とも称されるこの場所は、気軽に行ける距離ではないからこそ、いつかは訪れたいと願っていた憧れの温泉地。 期待に胸を膨ませ、博多から山陽新幹線で新神戸駅へ。そこからバスに乗り換えて揺られること約30分。車窓の景色が都会のビル群から緑豊かな山々へと変わっていく様に旅情をかき立てられながら、ついに情緒あふれる温泉地の入り口に到着しました。
目に飛び込んできたのは、有馬川に架かる朱色の欄干が美しい「太閤橋」。ここから宿泊するホテルへ向かうため、迎えのミニバスに乗り込んだのですが、この車中での出来事が、私たちの有馬温泉への見方を大きく変えることになったのです。
第一章:太閤橋の謎 – 運転手さんが教えてくれた、知恵と戦略の物語
ミニバスがゆっくりと走り出し、温泉街の象徴である「太閤橋」を渡り始めました。有馬温泉といえば、天下人・豊臣秀吉が愛した場所。私はてっきり、その縁から名付けられたものだと信じて疑いませんでした。
「この太閤橋は、やっぱり豊臣秀吉の縁から名付けられたんですよね?」
何気なく運転手さんにそう尋ねたことが、思いがけない有馬温泉の深掘りツアーの始まりでした。私の問いに、ハンドルを握る運転手さんはにこやかに頷き、そしてこう続けたのです。
「ええ、その通りなんですが、実はこの橋、昔は違う名前やったってご存知ですかな?」
その一言に、私と妻は顔を見合わせました。運転手さんによると、もともとこの橋は「太閤橋(たいこうばし)」ではなく、「太鼓橋(たいこばし)」という名前だったというのです。その名の由来は、有馬川の上流にある「太鼓滝(たいこだき)」から。その滝の下流にある橋ということで、その名がつけられていたそうです。
では、なぜ「太鼓」が「太閤」に変わったのか。その背景には、この日本を代表する温泉地が直面した、ある厳しい現実がありました。
今でこそ国内外から多くの観光客が訪れ、賑わいを見せる有馬温泉ですが、数十年前、深刻な不況の波に飲まれ、客足がぱったりと途絶えてしまった時期があったといいます。「日本三名泉」という強固なブランドだけでは、どうにもならない時代の大きなうねり。温泉街全体が深い危機感に包まれる中、人々は知恵を絞り、必死に再生の道を模索しました。
その中で生まれた起死回生の一手が、「太鼓橋」を「太閤橋」へと改名する、というアイデアでした。有馬温泉にとって「中興の祖」ともいえる大恩人、豊臣秀吉。この歴史的事実とストーリーをもっと観光の前面に押し出すべきではないか、と。それは単なる名称変更ではなく、有馬温泉のアイデンティティを再定義し、訪れる人々に明確な物語を提示する、一大ブランディング戦略の幕開けでした。
このアイデアは見事に採用され、橋の名前は「太閤橋」に生まれ変わりました。さらに、その物語を補強するように、橋の近くには秀吉公の銅像が建てられ、少し離れた場所には、彼が愛した妻・ねね様の銅像と、その名も「ねね橋」が作られたのです。
ホテルに着くまでの短い時間、私の素朴な疑問から始まった運転手さんの熱のこもった話に、私たちはすっかり引き込まれていました。それは、歴史の上に胡坐をかくのではなく、歴史を現代に活かし、未来へと繋げていこうとする強い意志の物語でした。
第二章:金泉・銀泉の誕生秘話 – 極上の湯に込められた、時代の空気と長寿への願い
有馬温泉の最大の魅力は、なんといってもそのユニークな泉質。一つの温泉地に、全く異なる二種類の源泉が湧き出ていることは世界的にも非常に珍しいといいます。一つは、空気に触れると酸化して鮮やかな赤褐色に変わる「金泉」。そしてもう一つが、無色透明の「銀泉」です。
私たちは滞在中、日帰り温泉施設の「金の湯」で名物の金泉を堪能し、宿泊したホテルでは、ゆっくりと銀泉に浸かるという、この上ない贅沢を味わうことができました。
タオルが赤く染まるほど濃厚な金泉は、鉄分と塩分を豊富に含み、身体の芯から温めてくれる力強い「療養の湯」。一方の銀泉は、炭酸泉と放射能泉からなり、血行を促進してくれる優しい湯。このコントラストこそが、有馬温泉の奥深さなのでしょう。
そして、この「金泉」「銀泉」という美しい名前にも、実は秘密があることを、例の運転手さんが教えてくれました。
「金泉も銀泉も、昔はもっと素朴な呼び方やったんですよ」
彼によれば、金泉はもともと、その見た目から「赤湯(あかゆ)」や「泥湯(どろゆ)」などと呼ばれていたそうです。そして、銀泉は単に「炭酸泉」と。しかし、町おこしの一環で、温泉の呼び名にも工夫を凝らすことになったのです。
当時、テレビでは100歳を超える双子の姉妹「きんさん・ぎんさん」が国民的な人気を博していました。彼女たちの元気で愛らしい姿は、日本中に長寿への明るい希望を与えていました。
「金」「銀」という響きは、豪華さだけでなく、この「きんさん・ぎんさん」が象徴する「健康」や「長寿」のイメージと見事に結びついたのです。有馬の湯に浸かることで、心も体も健やかになり、長生きできる。そんな願いを込めたネーミングは、人々の心に深く、そして温かく浸透していきました。
ミニバスの運転手さんとの会話がなければ、私たちはきっと、この興味深い誕生秘話を知ることもなく、ただ「気持ちのいいお湯だったね」で終わっていたかもしれません。偶然の出会いが、旅を何倍も豊かなものにしてくれました。
第三章:温泉街散策で感じた「一枚岩」の力 – 統一された世界観がもたらす没入体験
太閤橋から始まる「秀吉ストーリー」と、「金泉・銀泉」というキャッチーなネーミング。有馬温泉の魅力は、これらの点と点が線となり、さらには温泉街全体を包み込む「面」となって展開されている点にあります。
妻と二人、湯坂道をそぞろ歩けば、その徹底ぶりに感心させられます。土産物屋の軒先には、秀吉の馬印であった「千成瓢箪」をモチーフにした置物が並びます。老舗の和菓子屋では、秀吉が茶会で用いたとされる天目茶碗を模したお菓子が売られています。
それは、まるで温泉街全体が一個のテーマパークのようです。しかし、作り物めいた安っぽさは全くありません。一つ一つの店舗や施設が、有馬温泉と豊臣秀吉という、実際にあった歴史的な結びつきを深く理解し、リスペクトした上で、自らの商売にそのエッセンスを取り入れている。だからこそ、街全体に統一感がありながらも、それぞれの個性が失われていないのです。
個々のお店が単独で頑張るだけでは、これほどの世界観は作り出せないでしょう。そこには、「有馬温泉を盛り上げる」という共通の目的意識のもと、地域全体が「一枚岩」となって取り組んできたであろう、長年の努力と協力の歴史が透けて見えます。
観光産業の成功は、決して個店の力だけでは成し遂げられません。地域ぐるみで明確なビジョンを共有し、いかに本気で、そして楽しみながら取り組むことができるか。有馬温泉の街歩きは、私にその成功の秘訣を雄弁に物語っていました。
第四章:日本最古の湯のプライドと、未来を見据える覚悟
今回の旅で私が最も心を揺さぶられたのは、有馬温泉が持つ「強烈なまでの強み」と、それに安住しない「健全な危機感」の共存です。
有馬温泉の歴史は驚くほど古く、『日本書紀』にもその名が登場する、正真正銘「日本最古の湯」の一つ。そして、天下人・豊臣秀吉が愛したという、他の追随を許さない強力なストーリー。これだけの歴史とブランドがあれば、黙っていても客は来るだろう、と考えるのが普通かもしれません。
しかし、有馬温泉の先人たちはそうではなかったのです。彼らは、時代の変化を敏感に感じ取り、ブランドを磨き続ける努力を怠りませんでした。「太閤橋」への改名も、「金泉・銀泉」のネーミングも、すべては「このままではいけない」という危機感から生まれた、極めて攻撃的で戦略的な「革新」でした。
伝統とは、ただ守るものではなく、時代に合わせて革新し続けることで、初めて未来へと受け継がれていくものなのです。有馬温泉は、そのことを身をもって証明しています。日本最古の湯というプライドと、常に未来を見据えるベンチャースピリット。この両輪が、有馬温泉を今なお日本最高の温泉地の一つたらしめているのでしょう。
おわりに
初めて訪れた有馬温泉。それは、単に素晴らしい泉質と風情ある街並みを楽しむだけの旅ではありませんでした。ホテルへ向かうミニバスの車中で、私の何気ない一言から始まった、一本の橋の名前、二つの湯の呼び名に隠された、知られざる町おこしの物語。それは、危機を乗り越えるための人間の知恵と、地域が一体となって未来を切り拓いていくことの尊さを教えてくれる、感動的なドキュメンタリーでもありました。
もしあなたが次に有馬温泉を訪れる機会があれば、ぜひ「太閤橋」の上で立ち止まり、その名前に込められた人々の想いに耳を傾けてみてください。そして、「金の湯」に浸かりながら、その温かさの向こうにある長寿への願いを感じてみてほしいと思います。きっと、ただ温泉に入るだけでは得られない、深く、そして豊かな体験が待っているはずです。
この素晴らしい温泉地が、これからもその伝統と革新の精神を受け継ぎ、100年後、1000年後も人々を癒し、魅了し続けることを心から願っています。妻と二人、心身ともに満たされ、再訪を固く誓い合いました。赤く染まったタオルを大切な土産に、私たちは再びバスと新幹線を乗り継ぎ、九州への帰路につきました。車窓から遠ざかる六甲の山並みを眺めながら、旅の発見を胸に刻んだ、忘れられない三泊四日の旅となりました。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役