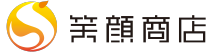「目黒のさんま」という有名な落語があります。海から遠い目黒で食べたさんまが一番美味しいと勘違いしてしまう、お殿様のユーモラスな物語。この噺(はなし)がきっかけとなり、今では目黒の町おこしにまで発展しています。
もちろん、目黒でさんまが獲れるわけではありません。しかし、落語のせいでしょうか、一生に一度は、「目黒でさんまが食べたい」という衝動に駆られていたのです。そして先日、ついにその長年の念願が叶いました。
ついに実現!目黒で味わった絶品の「新さんま」
訪れたのは、目黒の活気ある居酒屋。メニューに「新さんまの塩焼き 1300円」の文字を見つけた時、心の中でガッツポーズをしました。旬のさんまとしては、このご時世、むしろ安いのかもしれません。
運ばれてきたさんまは、想像以上に立派な大きさでした。炭火でじっくりと焼かれた皮はパリッと香ばしく、箸を入れると、じゅわっと良質な脂が溢れ出します。一口食べれば、口の中いっぱいに広がる濃厚な旨味と香り。まさに、待ち焦がれた秋の味覚そのものです。
「生」だからこそ、骨からの身離れも驚くほど綺麗。するりと骨が外れる様に、その鮮度の良さが伝わってきます。やっぱり、旬のさんまは最高だなと、しみじみと感じ入りました。
帰り道、スーパーの鮮魚コーナーを覗くと、そこにも活きの良いさんまが並んでいました。1匹250円。こちらもなかなか大きいサイズです。どうやら、今年は豊作のよう。そういえば、ここ数年、不漁のニュースばかりで、満足にさんまを食べていなかったような気がします。
久しぶりに心から「美味しい」と思えるさんまに出会えたこと。旬の食材は、私たちの心も体も豊かに、そして元気にしてくれるのだと改めて実感した夜でした。
そもそも、なぜ「目黒のさんま」?落語が描く江戸の粋
では、なぜ海のない目黒がさんまの代名詞になったのでしょうか。その答えは、江戸時代から続く古典落語「目黒のさんま」の中にあります。
あらすじ:殿様の素朴な感動と盛大な勘違い
ある日、一人の殿様が鷹狩りのために目黒を訪れます。ちょうどお腹が空いた頃、どこからともなく煙とともに、なんとも香ばしい匂いが漂ってきました。匂いの元は、農家が七輪で焼いていたさんま。
お腹を空かせた殿様は「あれが食べたい」と所望しますが、家来は「さんまは下魚(げぎょ)。庶民が食べる魚で、殿のお口には合いませぬ」と大慌て。しかし、殿様の強い希望に根負けし、農家からさんまを分けてもらうことになります。
農家で焼いたさんまは、脂を抜いたり骨を取ったりといった面倒な下処理は一切なし。炭火で豪快に焼いただけの、いわゆる「隠亡焼き(おんぼうやき)」。しかし、これが殿様の口に合ったのです。したたる脂の旨味、香ばしい香り。殿様は初めて味わうその美味しさに、いたく感動しました。
後日、屋敷に戻った殿様は、あの味が忘れられず、家来にさんまを所望します。家来たちは大張り切り。日本橋の魚河岸で最高級のさんまを仕入れ、万全を期して調理に取り掛かります。
「脂は体に毒」とすっかり抜き、「骨が喉に刺さると大変」と小骨一本残らず取り除く。そして、品よく蒸し物にして殿様の前に差し出しました。
しかし、それを食べた殿様は、なんとも不満げな顔。そして、こう尋ねます。 「このさんま、どこで求めたものじゃ?」 家来が「はっ、日本橋の魚河岸にて、最上のものを」と胸を張って答えると、殿様はこう言い放ったのです。
「それはいかん。さんまは目黒に限る」
これが、この噺の有名なオチです。
落語に込められた風刺と教え
この噺は単なる笑い話ではありません。そこには、江戸の庶民の目線から見た、鋭い社会風刺が込められています。
・身分制度への批判:世間知らずで、物事の本質を見抜けない殿様をユーモラスに描き、権威を笑い飛ばしています。
・庶民の知恵:高級な食材や凝った調理法よりも、旬のものをシンプルにいただく方が美味しいという、庶民の生活に根差した知恵を称賛しています。
・形式主義への皮肉:「体に良いから」「危険だから」と、良かれと思って手を加えすぎた結果、本来の美味しさを損なってしまう。そんな形式主義や過剰な忖度への皮肉が効いています。
この落語の背景には、実際に三代将軍・徳川家光が目黒で鷹狩りをした際に、茶屋に立ち寄ったという史実があり、物語にリアリティを与えています。
落語から現実へ!町を盛り上げる「目黒のさんま祭り」
そして、この古典落語は現代に受け継がれ、地域を盛り上げる一大イベントへと発展しました。現在、目黒では毎年秋に2つの大規模な「さんま祭り」が開催されています。
[1] 目黒のさんま祭り(品川区上大崎・目黒駅前商店街)
・毎年9月の第1または第2日曜日に開催。
・岩手県宮古産の新鮮なさんまが炭火で焼かれ、無料で振る舞われます。
[2] 目黒区民まつり「目黒のSUNまつり」(目黒区・田道広場公園)
・目黒区民まつりの一環として開催。
・こちらは宮城県気仙沼産のさんまが提供されます。
どちらの祭りも、落語の世界さながらに炭火で焼かれた絶品のさんまを味わおうと、毎年多くの人々でごった返します。落語の実演なども行われ、まさに「目黒のさんま」を五感で体験できるイベントとして定着しているのです。一つの物語が、時を超えて人々を繋ぎ、町の文化を創り上げている素晴らしい事例と言えるでしょう。
今年のさんまは本当に「豊漁」?食卓を揺るがす近年の状況
私がスーパーで見たように、今年はさんまが豊漁だというニュースを耳にします。しかし、その背景は少し複雑です。
2024年〜2025年の状況:「奇跡の回復」と楽観できない現実
2025年8月29日の報道によると、東京・豊洲市場でのさんまの卸売数量が夏場としては異例の117トンに達し、首都圏の店頭にも大ぶりで脂ののったさんまが並び始めました。全国さんま棒受網漁業協同組合によれば、「国際的な資源管理が進んでいることや海中の餌の状態がよいことが要因とみられ、近年にないスタート」とのことです。
確かに、2024年の水揚げ量も前年比で増加し、「奇跡の回復」とまで言われました。しかし、これはあくまで「近年の深刻な不漁からの一時的な回復」であり、決して楽観視できる状況ではありません。
歴史的な不漁という大きな流れ
日本のさんま漁獲量は、2008年のピーク時には約40万トンありましたが、近年は激減。2022年には過去最低の約1万8000トンにまで落ち込みました。2024年に回復したといっても約3万9千トンで、ピーク時の10分の1に過ぎません。
不漁の主な原因
・海水温の上昇:地球温暖化の影響で、さんまの回遊ルートが日本の沿岸から遠い沖合に変化してしまいました。
・国際的な乱獲問題:日本の排他的経済水域(EEZ)の外側の公海で、中国や台湾の漁船が、日本に来遊する前のさんまを大量に漁獲していることが大きな問題となっています。
2024年の回復は、たまたま日本近海に漁場が形成されたことや、中台の漁船が漁獲枠に早く達して漁を終えたことなど、一時的な好条件が重なったためと考えられています。水産庁の見通しでも、2025年のさんま漁は昨年並みの低水準と予測されており、根本的な課題は解決していないのです。
今年、私たちが美味しいさんまを手にしやすい価格で味わえるのは、本当に幸運なことなのかもしれません。この一匹に感謝しながら、じっくりと味わいたいものです。
「物語」が町を元気にする!全国に広がる町おこしの輪
「目黒のさんま祭り」のように、落語や昔話といった「物語」を活かした町おこしは、日本全国で素晴らしい成功を収めています。
・桃太郎伝説(岡山県):「うらじゃ」という独特の踊りが特徴の「おかやま桃太郎まつり」は県下最大級のイベントに成長。「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」として日本遺産にも認定されています。
・かぐや姫伝説(静岡県富士市):市に伝わる「富士山へ帰るかぐや姫伝説」を基に、「富士山かぐや姫ミュージアム」を設立。観光PR大使「かぐや姫」を選出するなど、物語の世界観を大切にした町づくりを進めています。
・小栗判官伝説(茨城県筑西市):地域に伝わる伝説を再現した武者行列が人気の「小栗判官まつり」。住民が主体となって始まったイベントが35年以上も続く、地域密着型の成功例です。
これらの成功に共通するのは、単に有名な物語の名前を借りるのではなく、その土地ならではの歴史や解釈を大切にし、住民が誇りを持って参加している点です。物語の持つ力を活用し、地域の魅力を再発見し、文化を未来へ継承していく。これこそが、持続可能な町おこしの鍵なのでしょう。
おわりに
目黒で食べた一匹のさんま。その美味しさへの感動から始まった探求は、江戸の落語、現代の祭り、そして地球規模の環境問題、さらには全国の地域振興へと繋がっていきました。
旬の食材を味わうということは、ただ単に「美味しい」と感じるだけでなく、その背景にある豊かな文化や歴史、人々の営み、そして私たちが直面する課題にまで思いを馳せるきっかけを与えてくれます。
「さんまは目黒に限る」——。 殿様の盛大な勘違いから生まれたこの言葉は、今や、食文化と物語が地域を豊かにすることを証明する、魔法の合言葉になったのかもしれません。 皆さんもこの秋、旬の味覚を楽しみながら、その裏に隠された物語を探してみてはいかがでしょうか。きっと、いつもより深く、味わい深い食卓になるはずです。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役