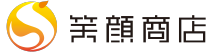プロローグ:大自然の恵みと、招かれざる客
先日、友人が営む農園の手伝いに行ってきました。澄んだ空気と力強い太陽の光を浴びて、トマト、トウモロコシ、ナス、ピーマン、ズッキーニが生き生きと育っています。有機農法にこだわり、愛情を込めて育てられた野菜は、どれも宝石のように輝いて見えました。
しかし、そんな美しい畑には、深刻な悩みがありました。夜な夜な現れる、野生動物たちです。鹿、猪、アライグマ…。彼らにとってはご馳走なのでしょうが、農家にとっては丹精込めて育てた作物を一夜にして台無しにしてしまう「天敵」です。柵を立て、対策を講じても、彼らの執念と知恵にはキリがありません。「どうしたものかな…」と嘆く友人の横顔が、この問題の根深さを物語っていました。
その翌日、街を歩いていると、ふと目に留まった一軒の雑貨屋。ショーウィンドウに飾られていたのは、美しい光沢を放つ革製品でした。手に取ってみると、それは驚くほどしなやかで、吸い付くような手触り。タグには「鹿革」と書かれていました。
「鹿か…!」
畑を荒らす、あの鹿。しかし、革製品の世界では、豚や牛よりも高級な素材として扱われている。この瞬間、頭の中に一つのアイデアが閃きました。もしかしたら、農家の悩みの種である野生動物は、新たなビジネスチャンスになるのではないか? これは、単なる思いつきなのか、それとも現実的な可能性を秘めているのか。私は、その答えを探るべく、ジビエレザーの世界を調べてみることにしたのです。
そもそもジビエレザーって何がすごいの?多様な革の世界
「革」と一言で言っても、その種類は様々です。まずは、それぞれの革が持つ個性とポテンシャルを見ていきましょう。
私たちの暮らしに最も近い「牛革・豚革・羊革」
実用性で言えば、やはり王者は牛革です。高い耐久性と厚みを持ち、バッグや靴、財布など、あらゆる製品に使われる万能選手。私たちの生活に最も浸透している革と言えるでしょう。
一方、豚革は軽くて通気性が良く、摩擦に強いのが特徴。日本では馴染み深い素材で、高級ブランドのバッグの内張りなどにも使われます。そして羊革は、圧倒的な軽さと柔らかさが魅力。しっとりと肌にフィットする感触は、高級なジャケットや手袋に最適です。
秘められた力を持つ「鹿革」と「猪革」
ここで、今回の主役である鹿革の登場です。鹿革の最大の特徴は、「革のカシミア」とも呼ばれるほどの極めて高い柔軟性と軽さにあります。さらに驚くべきは、吸湿性・放湿性の高さ。水に濡れても変形しにくく、湿気に強いという、他の革にはない優れた特性を持っています。アウトドア用品や日本の伝統工芸品「印伝」などに使われてきたのも納得です。
そして、もう一つの主役が猪革。猪の皮は、野生ならではの傷が多いものの、その耐久性は牛革をもしのぐと言われています。革の繊維が非常に密で、摩擦や水、引っかき傷に滅法強い。軽量でありながら「孫の代まで使える」と称されるほどの堅牢さを誇ります。使い込むほどに光沢を増し、風合いが深まっていくのも大きな魅力です。
▼主要な革の比較表
| 革種 | 耐久性 | 柔軟性・軽さ | 通気性・吸湿性 | 水濡れ耐性 | 主な用途 |
| 牛革 | 非常に高い | 適度 | 高 | 中 | 万能(バッグ、靴、財布など) |
| 豚革 | 高い | 高い・薄い | 高 | 低 | 内張り、軽量品、スポーツ用品 |
| 羊革 | やや低い | 非常に高い | 高 | 低 | ジャケット、手袋、衣料 |
| 鹿革 | 高い(手入れ必要) | 非常に高い | 極めて高い | 非常に高い | アウトドア、伝統工芸、アクセサリー |
| 猪革 | 非常に高い | 軽量 | 良い | 高い | アウトドア、高耐久な小物 |
この他にも、ワニ革や山羊革、熊革、アライグマ革など、世界には多種多様な革が存在します。しかし、特に鹿革と猪革は、日本の里山が抱える鳥獣被害という課題と密接に結びついており、特別なポテンシャルを秘めているのです。
なぜ今、ジビエレザーが注目されるのか?
ジビエレザービジネスの可能性は、単なる革の特性だけに留まりません。現代社会が抱える課題と、消費者の価値観の変化が、大きな追い風となっています。
・社会課題の解決に繋がる「エシカル消費」 : 現在、日本全国で駆除される鹿や猪は年間約100万頭。そのうち、食肉(ジビエ)として利用されるのはわずか1割程度で、皮に至ってはそのほとんどが廃棄されているのが現実です。農作物被害額は年間約158億円にも上ります。この「害獣」として駆除された命を、価値ある製品として再生させるジビエレザーは、生命への感謝と資源の有効活用を体現するものです。環境問題や持続可能性に関心が高い現代の消費者にとって、そのストーリーは大きな魅力となります。
・国も後押しする「6次産業化」の流れ : 農家(1次産業)が、加工(2次産業)から販売(3次産業)までを一貫して手掛ける「6次産業化」。これは、農家の所得向上や地域活性化の切り札として、国も補助金などで積極的に支援しています。ジビエ革ビジネスは、まさにこの6次産業化のモデルケースとなり得るのです。
・拡大する革製品市場と多様化するニーズ : 世界の革製品市場は成長を続けており、2032年には8,553億ドルに達すると予測されています。その中で、大量生産品にはない独自性や希少性、物語性を持つ製品への需要が高まっています。一つひとつ傷や風合いが異なるジビエレザーは、まさに「世界に一つだけ」を求める消費者の心に響く素材なのです。
農家がジビエ革ビジネスを始めるには?現実的な道のりと課題
では、農家がこのビジネスに参入するには、具体的にどうすればよいのでしょうか。そこには、乗り越えるべき課題と、成功への戦略があります。
乗り越えるべき3つの壁
[1] 技術の壁(品質の不安定さと加工技術) 野生動物の皮は、生きていた時の傷やダニの跡が多く、品質が一定ではありません。また、皮を腐らない「革」へと生まれ変わらせる「鞣し(なめし)」には、高度な専門知識と設備が必要です。これを個人で行うのは非常にハードルが高いと言えます。
[2] 経営の壁(初期投資と販路開拓) 原皮を冷凍保存する設備や加工機械には、数百万円単位の初期投資がかかる場合があります。また、ジビエレザーはまだニッチな市場。どのようにして製品をPRし、販売していくかという販路開拓も大きな課題です。
[3] 供給の壁(季節性と需給バランス) 狩猟には猟期(多くは11月〜2月)があり、一年を通して安定的に原皮を確保することが難しい場合があります。捕獲量も天候や地域によって変動するため、生産計画が立てにくいという側面もあります。
成功への4つの戦略
これらの壁を乗り越えるため、次のような戦略が考えられます。
❶ スモールスタートで始める : 最初から全ての設備を揃える必要はありません。まずは猟友会などと連携して原皮を確保し、鞣しは専門の加工業者(タンナー)に外注することから始めましょう。リスクを抑え、市場の反応を見ながら少しずつ規模を拡大していくのが賢明です。
❷「物語」で差別化する : 「この革は、〇〇町の畑を守るために捕獲された鹿から生まれました」。このようなストーリーは、製品に唯一無二の価値を与えます。トレーサビリティ(生産履歴の追跡)を明確にし、購入者がその背景を知ることができるようにすることも、信頼と共感に繋がります。
❸ 連携体制を築く(仲間を見つける) : 農家一人で全てを抱える必要はありません。地域の猟友会、専門のタンナー、革製品をデザイン・製作してくれるクラフト作家、販売に協力してくれる店舗や自治体など、様々なパートナーとの連携が成功の鍵を握ります。
❹ 補助金を賢く活用する : 国や自治体には、「6次産業化支援事業」や「地域活性化補助金」など、様々な支援制度があります。初期投資の負担を軽減するためにも、これらの制度を積極的に情報収集し、活用しましょう。
希望の光!全国に広がる成功事例
「本当にそんなビジネスが成り立つのか?」と思うかもしれません。しかし、すでに全国各地で、農家や地域が主体となった成功事例が生まれています。
・株式会社クイージ(島根県など) 地域の猟師や婦人会と連携し、食肉加工だけでなく革製品の開発・販売までを手掛けています。高級缶詰やレザークラフトなど、多角的な商品展開で地域に新たな雇用を生み出しています。
・広島ジビエレザープロジェクト(広島県) 地域のタンナーと連携し、高品質な猪革・鹿革を「広島ジビエレザー」としてブランド化。その品質の高さから、多くのクリエイターに支持されています。
・サイバー農家 宮川将人氏 ICT(情報通信技術)を駆使して、捕獲から加工、販売までの情報を追跡できるトレーサブルなジビエ生産を実現。皮革製品への展開はもちろん、骨や内臓まで堆肥化する「完全循環システム」を構築しています。
これらの事例に共通しているのは、地域ぐるみでの連携、品質へのこだわり、そして廃棄される命を価値に変えるという強い想いです。
結論:農家だからこそ、このビジネスには価値がある
改めて、最初の問いに戻りましょう。「農家がジビエ革ビジネスで成功する可能性は?」
私の結論は、**「条件は揃っており、可能性は非常に高い」**です。
もちろん、簡単な道のりではありません。しかし、市場の追い風、国の支援、そして何より、このビジネスが持つ社会的意義の大きさが、挑戦する価値を示しています。
年間50頭の鹿を処理した場合、加工費などを差し引いても年間50万円程度の利益が見込める、という試算もあります。これはあくまで一例ですが、農業収入にプラスアルファの収益をもたらす可能性は十分にあります。
しかし、このビジネスの本当の価値は、利益の額だけでは測れません。
・農地被害の実体験から生まれる、強い課題意識。
・猟友会など、地域との既存のネットワーク。
・農閑期を活用できる、新たな収入源。
これらは、他の誰でもない、農家だからこそ持つことができる最大の強みです。
畑を荒らす厄介者。しかし、その命を無駄にせず、感謝と共に新たな価値を与える。それは、自然と向き合い、生命を育む「農家」という仕事の本質にも通じるのではないでしょうか。
友人の畑で見た、野生動物たち。彼らとの共存は難しい問題です。しかし、見方を変えれば、彼らは地域の課題を解決し、新たな文化と産業を生み出す「宝物」になるかもしれない。あなたの地域の畑にも、そんな可能性を秘めた宝物が眠っているかもしれません。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役