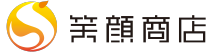先日、福岡を訪れた際にグランドハイアット福岡に宿泊しました。
噂に違わぬ素晴らしいホテルですね。洗練された客室環境、そしてスタッフの方々のきめ細やかな接客サービス。365日ホテル暮らしをしている知人が「ハイアットグループの中でここが一番バランスが取れている」と絶賛していましたが、その理由がよく分かりました。
さて、そのホテルの近くに、かなり有名な鰻料理店があるということで、期待に胸を膨らませて翌日の昼食に訪れました。
私が注文したのは、お店のおすすめである「せいろ蒸し御膳」。そして妻は「鰻と牛肉の石焼御膳」を。
運ばれてきたせいろ蒸しは、蓋を開けると湯気とともに良い香りが立ち上り、見た目にも食欲をそそります。
「これは美味しそうだ」
期待を込めて鰻を一口。しかし、その瞬間に「あれ?」という違和感が。
「これ、本当に蒸してる?なんだか少し水っぽい…?」
私がこれまで味わってきた他店のせいろ蒸しとは明らかに違う食感で、「これがこの店のスタイルなのか?」と少し戸惑ってしまいました。
しかし、御膳にはひつまぶしのように出汁がついていました。気を取り直して、その出汁をかけて食べてみると…
「これはいける!」
出汁の風味と相まって、先ほどの水っぽさが旨味に変わり、美味しくいただくことができました。
ただ、素直に喜べない自分がいました。本来の食べ方であるはずの「そのまま」の状態では今一つで、出汁をかけるというアレンジでようやく完成する。なんとも微妙な気持ちです。
守破離の「離」から入ってしまった料理?
この体験から、ふと「守破離(しゅはり)」という言葉が頭に浮かびました。
・守(しゅ): 師の教えや型を忠実に守り、基本を確実に身につける段階。
・破(は): 既存の型を破り、他に学び、自分に合った新しい型を作る段階。
・離(り): 型から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階。
このお店のせいろ蒸しは、もしかすると伝統的な型から離れた、新しいスタイルを目指した「離」の料理なのかもしれません。しかし、そのためには揺るぎない「守」の段階、つまり基本が完璧でなければならないはずです。
人気漫画『鬼滅の刃』に登場する上弦の陸、獪岳(かいがく)という鬼を思い出しました。彼は雷の呼吸の使い手でありながら、基本である「壱ノ型」を習得できませんでした。基本ができていないのに、他の型だけを習得して強さを求めた彼の姿が、今回の鰻と重なって見えたのです。
妻が注文した「鰻と牛肉の石焼御膳」も、美味しいことは美味しいのですが、鰻と牛肉が必ずしもお互いを高め合っているとは言えず、どこか食べ合わせの妙を感じてしまいました。
新しさを生み出すための「温故知新」
この一連の体験から、もう一つ「温故知新」という言葉が心に浮かび上がりました。
「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る、以って師と為るべし」
これは、ただ古いものを懐かしむのではなく、過去の知識や経験を深く研究し、そこから新しい知識や道理を発見することの重要性を説いています。
なぜ、鰻はせいろで蒸されてきたのか。その調理法が長年愛されてきた理由、つまり「故き」を深く理解し、その本質を突き詰めた先にこそ、人々を本当に感動させる「新しき」、つまり画期的な商品やサービスが生まれるのではないでしょうか。
表面的な新しさや奇抜さに走る前に、今ある商品やサービスが存在する根本的な理由を考える。今回の鰻のせいろ蒸しは、そんな大切なことを改めて私に教えてくれた、味わい深い体験となりました。

髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役